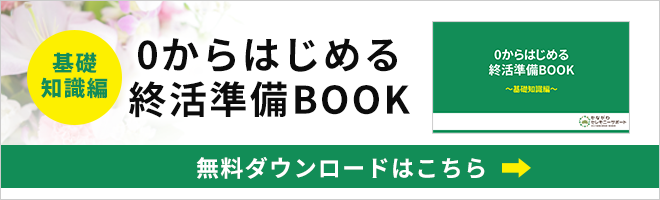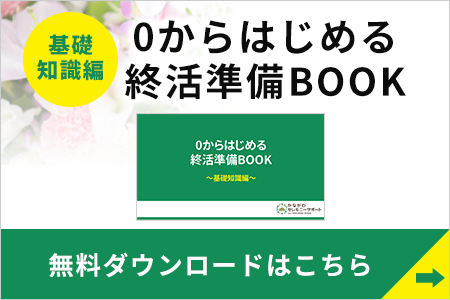家族葬はどこまでが呼ぶべき範囲?参列基準や参列時のマナーを紹介
大切なご家族を亡くされ、「親しい間柄のみで故人を見送りたい」と家族葬を選択される方もいらっしゃるでしょう。
その際に頭を悩ませるのは、「参列者はどこまで呼ぶべきか」ということではないでしょうか。
本記事では、家族葬における参列者の判断基準やマナーについて解説します。
故人との最後のひとときを、大切な方々と心静かに過ごすための参考にしてください。
目次
家族葬の参列者はどこまで呼ぶべき?

家族葬の参列者の範囲に明確な定義はなく、どこまで呼ぶかはご家族に判断がゆだねられているのが現状です。
「家族葬」という言葉から、故人の親族しか参列できないと考えがちですが、親族に限定せず、故人と親しかった友人や知人を招くケースもあります。
参考として、公正取引委員会の葬儀の取引に関する実態調査報告書では、以下のように明記されています。
公正取引委員会が公表している家族葬の定義
・親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席して執り行う葬儀
・通夜・告別式、火葬等は一般葬と同様に執り行われる
・参列者50人未満の葬儀
上記でも、あくまで参列者と故人の間柄に言及しているのみで、どこまで呼ぶべきか? という点には触れられていません。
また、参列者数も50人未満と大まかな決まりしかなく、実情としても数人で執り行う場合もあれば、30~50人ほど呼ぶ場合もあります。
参照元:公正取引委員会「(平成29年3月22日)葬儀の取引に関する実態調査報告書p36」
関連記事:家族葬とは?小規模の葬儀を執り行うメリット・デメリットも
家族葬で呼ぶか迷う方がいる場合は?
家族葬に呼ぶかどうかの判断基準として、「故人が最後に会いたいか」という観点から考えることが挙げられます。
生前の故人との間柄を思い出し、故人がどのように思うか想像してみましょう。
この点から考えても迷う場合には、その方は葬儀に招くのがおすすめです。
もしも迷った末に呼ばなかった方が自宅へ弔問に訪れた際に、納得できる理由がなければ相手の気分を害する可能性もあります。
また、葬儀に呼ぶかの判断が曖昧なまま選別すると、周囲からの理解も得づらくなるでしょう。
どうしても判断ができない方は、葬儀に招くのが賢明です。
家族葬でどこまで呼ぶかは参列者の人数を参考に
家族葬において参列者の線引きに悩む場合には、どの程度の規模の葬儀を想定しているのかを基準に考えるのも一つの手です。
以下の表で、人数に対して目安となる参列者の範囲をまとめました。
人数に対する参列者の範囲
| 参列者の人数 | 目安となる参列者の範囲 |
| 10名程度 | 近しい親族(両親や兄弟、配偶者など) |
| 30名程度 | 幅広い親族(従妹や叔父、叔母、配偶者の家族など)と少数の親しい友人 |
| 50名程度 | 親族にくわえ故人と生前に親交のあった方(友人や恩師など) |
参列する人数が増えるほど、故人との交友関係の把握が難しくなる可能性があるため、連絡の不備などのトラブルが発生しないよう注意が必要です。
また、葬祭場の広さや葬儀の費用をあらかじめご家族内で固めておくと、参列できる人数が定まり、葬儀に呼ぶ参列者の範囲も絞りやすくなります。
家族葬でどこまで呼ぶか迷う場合に注意したいポイント

ここからは、参列者を限定する家族葬だからこそ起こりやすいトラブルを避けるために注意したい2つのポイントを紹介します。
呼ばない方にも連絡する
葬儀に呼ばない方には、「家族葬で執り行う旨」とともに「参列辞退の意向」を連絡することがマナーです。
参列辞退の連絡とは、葬儀への参列を遠慮してほしいという内容をご家族から伝えるものです。
親族はもちろん、故人と親交のあった友人や知人のなかには、「最後に故人と会いたい」と参列を希望する方も多くいらっしゃいます。
連絡をせずに家族葬を進めてしまうと、あとになって「なぜ呼んでくれなかったんだ……」と批判を受けかねません。
参列辞退の連絡によって理由をきちんと説明することで、こうした葬儀後のトラブル回避につながります。
故人を偲ぶ方への最低限のマナーとして、事前の連絡を徹底しましょう。
参列辞退の連絡なのか葬儀の案内なのか明確に伝える
親族や親交のあった方々に逝去のお知らせを伝える際に注意したいのは、参列辞退の意向、または葬儀の案内のどちらであるかを明確に伝えることです。
連絡を受けた側がこの点を明確に判断できる内容にしなければ、呼ばなかった方が葬儀の当日に間違えて参列する可能性があります。
参列辞退を伝える場合には、葬儀の詳細は記載せず、逝去のお知らせとともに近親者のみで家族葬を行う旨を伝えましょう。
家族葬当日に参列者が増えるといった混乱を避け、故人を静かに見送るためにも、葬儀に呼ばない方への連絡の内容には気をつけたいところです。
家族葬を執り行う際の流れ
家族葬の参列者に誰を呼ぶか決まったら、次は葬儀の手配を行います。
葬儀を執り行う際の具体的な流れは、以下をご確認ください。
家族葬を執り行う際の流れ
- 逝去・ご遺体の安置
- 葬儀社へ連絡
- 故人の関係者へ訃報と家族葬の案内
- 家族葬の打ち合わせ
- 湯灌・納棺
- 通夜・告別式
家族葬といっても、葬儀を執り行う際の流れに一般葬との違いはありません。
なお、上記で紹介した流れはあくまで基本的なものであり、故人やご家族の希望に応じて葬儀の内容は変更できます。
家族葬のメリット・デメリット

心残りなく故人を見送るために、葬儀方法はきちんと吟味したいものです。
そこで本項では、家族葬のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
故人やご家族の意向も踏まえつつ、最適な葬儀を行うための参考にしてください。
関連記事:家族葬とは?小規模の葬儀を執り行うメリット・デメリットも
家族葬のメリット
家族葬のメリットとしてまず挙げられるのは、故人とのお別れの時間をしっかりと取れるということです。
家族葬では参列者の数が少ないため、参列者の対応に要する時間が減ります。
そして減った時間の分だけ、故人との最後のひとときをゆっくり過ごせます。
また、葬儀費用を抑えられるのもメリットの一つです。
家族葬では葬祭場が小さくて済むうえに、参列者に用意するお返しの数も最小限に抑えられます。
これにより家族葬は、一般的な葬儀と比べて費用をかけずに執り行うことができるのです。
「故人とのお別れの時間を大切にしたい」「葬儀の費用負担を抑えたい」というご家族には、家族葬が向いているといえるでしょう。
家族葬のデメリット
故人とのお別れの時間を大切にできる一方で、参列者をどこまで呼ぶかの判断が難しく、「参列したかった……」という不満が起きやすい点は家族葬のデメリットです。
小規模な葬儀になるほど参列者の選定は困難になり、不満が起きやすくなります。
家族葬への理解を得るため、呼ばなかった方への細やかな対応が必要になることに負担を感じる方もいるでしょう。
また、参列者数が限られると、葬儀費用にもマイナスの影響を与えるかもしれません。
参列者が少なすぎると香典が減るため、実質的な費用負担は一般葬よりもかえって多くなる可能性が考えられます。
「参列者が少ないほうが静かだし費用も抑えられるから」と家族葬を安易に決めてしまうと、想定よりも葬儀後の対応や費用の負担が増え、後悔することになりかねません。
家族葬のメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、最適な葬儀の形式を検討してください。
家族葬の費用相場

家族葬の費用相場は、80万~100万円前後です。
一般葬の平均相場が160万~200万円前後であることを考えると、比較的費用が抑えられるのがおわかりいただけるでしょう。
家族葬の内訳には、火葬料や葬祭場使用料を含む葬儀の基本費用のほかに、参列者に振る舞う食事や香典に対する返礼品などが含まれます。
ただし、実際の費用は参列者の人数や会場の広さなどによっても変動するため、葬儀社に見積もりを依頼したうえで、サービス内容を十分に確認しましょう。
関連記事:家族葬の費用相場はいくら?費用を少しでも安くするためのコツは?
家族葬に参列する場合のマナー
以降では、参列者側のマナーを紹介します。
家族葬であっても、参列する場合のマナーに一般葬との大きな違いはありません。
服装は一般葬と同様、喪服や略礼服を着用し、カジュアルな服装や派手なアクセサリーは避け、清潔感のある身だしなみを心がけます。
香典を渡す場合は、1万円から5万円程度の金額が一般的です。
これ以外の金額を包む場合は「4」や「9」など死や苦を連想させる金額にならないよう、注意が必要です。
なお、最近の家族葬では、「親しい間柄で堅苦しい対応をしたくない」とご家族が香典を辞退するケースも増えています。
辞退された場合にはご家族の気持ちに寄り添い、無理に渡さないのがマナーです。
参列者を限定する家族葬では、呼ばれていない方をご家族の許可なく勝手に誘うのもマナー違反になります。
たとえ故人と関わりのある方であっても、参列者を絞ったご家族の意向を汲み、マナーを守って参列することが大切です。
親しい関係者のみで執り行う葬儀ではあるものの、故人を見送るための大切な儀式に変わりはありません。
参列時に失礼のないよう、マナーを心得て葬儀に臨みましょう。
関連記事:家族葬はどのような流れで進む?式を執り行う際の注意点は?
家族葬に参列しない場合のマナー
参列辞退の連絡を受けた場合にも、葬儀の対応に追われるご家族に迷惑がかからないよう、香典や弔問におけるマナーに注意する必要があります。
「家族葬に参列できないならせめて香典だけでも……」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、香典を送るとご家族は香典返しを用意しなくてはならず、かえって気を使わせてしまいます。香典を無理に渡したり、郵送したりすることは控えましょう。
ご家族が香典を辞退されていない場合には、参列する方に預けて渡してもらう、もしくは弔問の際に直接渡すのが一般的です。
自宅に弔問に伺う際は、ご家族の負担にならないよう注意が必要です。
ご家族は葬儀後も、相続の手続きや遺品の整理などで慌ただしくされています。
自宅に伺う際はあらかじめ連絡を取り、ご家族の都合を確認したうえで訪問してください。
家族葬に参列しないからといって、自分の都合だけで行動すると、ただでさえ忙しい状況のご家族に負担をかけてしまいます。
ご家族の気持ちに配慮し、適切なタイミングを見極めて弔意を伝えることが大切です。
まとめ
今回は、家族葬の参列者はどこまでの範囲で呼ぶべきか、参列者の判断基準やマナーとともに解説しました。
家族葬の参列者の範囲に明確な定義はなく、故人と親交のあった友人や知人を呼ぶなど、故人とご家族の意向が尊重されます。
一方で、参列者を限定するゆえに「呼ばれなかった」と批判が起きる場合もあります。
参列してもらう方の基準を明確にし、呼ばない方に対しても礼儀を尽くすことが、家族葬の理解を得るために重要です。
葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートでは、葬儀・ご供養のあらゆる相談を24時間365日サポートいたします。
後悔のない家族葬を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて