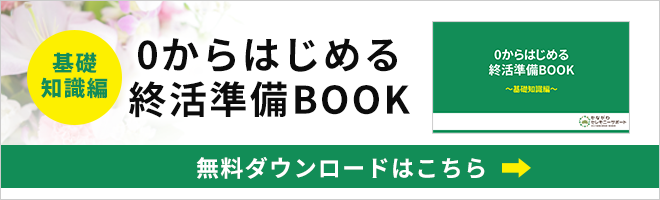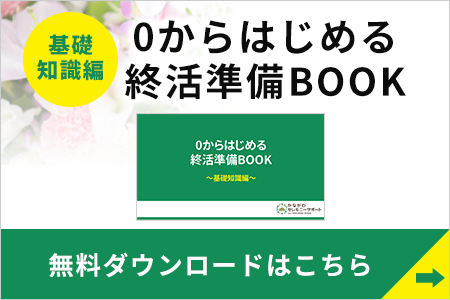葬式のあとの行事一覧|法事・法要の執り行い方とは
仏教では、葬式の当日以降も故人を偲ぶさまざまな行事が執り行われます。
法事・法要は種類が多く、それぞれに決まった流れが存在するため、正しい執り行い方を事前に身につけておいて損はありません。
そこで本記事では、葬式後に行われる法事・法要の種類と意味、また執り行う際の流れを解説します。
故人をきちんと弔うために、マナーを心得ておきたい方はぜひご覧ください。
葬式後の法事・法要とは
故人を偲び供養するための仏教行事は、葬式が終わったあとも続きます。
これらの行事は、一般的に「法事」または「法要」とよばれています。
両者は似た意味で使われがちですが、厳密には異なるものです。
法要とは、お寺の僧侶による読経や焼香など、故人の冥福を祈る仏教的な儀式のことで、追善供養ともいいます。
一方、法事は法要に加えて、その後の会食を含めた一連の行いを指します。
法事・法要は、故人の葬式以降、決まったタイミングで執り行われるもので、四十九日法要や一周忌などがその代表です。
現代では、供養のためだけでなく、親族が集まり故人を偲ぶ場としての意味合いも強くなっています。
なお、本記事では以降「法事」と「法要」をほとんど同義として扱います。
法事・法要の種類
仏式の法要は、大きく「忌日法要」「月忌法要」「年忌法要」の3つに分けられます。
故人が亡くなったあとの時期によって区別されており、それぞれに役割があります。
これらの法要は、故人を忘れず、感謝と祈りを込めて供養するための大切な儀式です。
形式にとらわれすぎず、それぞれの家庭や宗派の考え方に合わせて行うことが大切です。
忌日法要(きにちほうよう)
忌日法要は、亡くなってから49日目までに行われる法要の総称です。
たとえば、亡くなった日から7日ごとに行う初七日法要(しょなのかほうよう)や、四十九日法要がこれにあたります。
仏教では死後49日間、故人の魂が現世と死後の世界のあいだで迷っているとされ、この期間に複数の法要を執り行うことになっています。
月忌法要(がっきほうよう)
月忌法要は、故人が亡くなった月命日(毎月の同じ日)に行う供養です。
僧侶を招いて読経してもらうのが本来のかたちですが、現在では行われないことも多く、ご家族が自宅で手を合わせる程度にとどまるケースも珍しくありません。
また、地域や家の宗派によっても慣習は異なります。
年忌法要(ねんきほうよう)
年忌法要は、故人の命日に執り行われる法要です。
亡くなった1年後、2年後、6年後……と、決まった年に執り行われ、故人の冥福を改めて祈るとともに、親族が再び集う機会としての意味も込められています。
このような法要は、三十三回忌や五十回忌まで行われることが一般的です。
仏式の主要な法要一覧

法要の大まかな分類がわかったところで、個別の法要について詳しく見ていきます。
葬式が終わったあとに行われる行事を時系列順に紹介するので、参考にしてください。
初七日法要
初七日法要は、命日を含めて7日目に執り行われる、最初の忌日法要です。
仏教では、亡くなった直後の魂はまだ安定せず、現世と来世をさまよっているといわれています。
そのため、初七日は故人が最初の審判を受け、三途の川を渡る重要な節目の日とされており、無事に成仏できるよう祈る意味合いがあります。
法要では、僧侶の読経や焼香が行われ、供養後には「精進落とし」とよばれる食事を参列者に振る舞うのが一般的です。
命日から日が浅く、準備期間も限られるため、迅速な準備が求められます。
繰り上げ初七日
近年では、遠方からの参列や日程調整が難しいという事情から、葬儀と同日に初七日法要を行う「繰り上げ初七日」が主流になっています。
「式中初七日」と「戻り初七日」の2つの形式があり、式中初七日は葬儀の流れのなかで読経と焼香を行い、その後火葬場に向かいます。
一方、戻り初七日は火葬後に再び葬儀会場や自宅に戻って法要を行う形式です。
地域や宗派によって流れが異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。
四十九日法要
四十九日法要(しじゅうくにちほうよう)は、命日から数えて49日目に執り行われる法要で、仏教におけるもっとも重要な節目の日の一つとされています。
この日まで故人は7日ごとに生前の行いを裁かれており、49日目にようやく、極楽浄土に行けるかどうかの最終的な判決が下されます。
故人が安らかに旅立てるよう、四十九日法要は特に丁寧に準備する必要があるのです。
当日は多くの親族が集まり、僧侶による読経・焼香・会食などを通じて故人の成仏を祈ります。
この日をもって忌中が終わり、喪に服していたご家族が「忌明け」として日常生活に復帰する節目にもなります。
関連記事:後飾り祭壇の飾り方を知っていますか?設置~片付け方法を解説
一周忌
一周忌は、故人の命日から丸1年を迎える「祥月命日(しょうつきめいにち)」に行う年忌法要です。
四十九日法要で忌中が終わるのに続き、一周忌は喪中が終わる大切な節目とされます。
故人の逝去から1年という年月が過ぎ、ご家族の心も少しずつ落ち着いてくる時期でもあるため、大勢の親族を招いて盛大に供養するのが慣例です。
当日は僧侶による読経と焼香が行われ、墓参りや会食を通じて故人を偲びます。
参列しやすいよう、命日の前後の週末に日程を調整するとよいでしょう。
三回忌
三回忌は、故人が亡くなってから満2年目に執り行われる年忌法要です。
三回忌という名称から3年目に行うと誤解されがちですが、命日を一回忌として数えるため、2年目が該当します。
法要の形式は一周忌とほとんど同じで、僧侶による読経や焼香を行うのが一般的です。
ただし、招待する人数は一周忌より少ないことが多く、親族中心で行われます。
七回忌
七回忌は、故人の命日から数えて満6年目にあたる年忌法要です。
三回忌までと比べると、七回忌以降の法要は徐々に規模が縮小される傾向があり、近しい親族のみで執り行う家庭が増えます。
それでもなお、節目としての意味合いは強く、丁寧な供養が求められます。
内容は基本的に、一周忌・三回忌と同様です。
日程調整や案内など、準備には時間がかかる場合もあるため、余裕をもって計画を立てておくことが大切です。
十三回忌
十三回忌は、命日から数えて12年目に行う法要で、年忌法要としては中盤に差しかかるタイミングといえます。
この頃になると、法要の規模はさらに小さくなり、身内だけで静かに執り行うケースがほとんどです。多くの場合、命日の前後でお寺や自宅に親族が集まり、読経や焼香を行います。
法要のあとは会食しながら故人を偲び、ご家族や親族同士で近況を語り合う温かな時間が流れます。
十七回忌
故人の命日から数えて16年目には、十七回忌が行われます。
読経をあげてもらうために、親族がお寺に集まる、または自宅に僧侶を招きます。
この頃になると、故人を直接知らない世代も法要に参加するようになるため、仏教的な儀式の意味合いのほかに、親族のつながりを再確認する機会ともいえるでしょう。
三十三回忌
三十三回忌は、多くの宗派で「弔い上げ」として位置づけられる法要です。
これまで定期的に行われてきた年忌法要の締めくくりとしての意味があり、その折に個人の位牌を先祖代々の位牌に合祀する家庭も少なくありません。
法要の内容そのものはこれまでと大きく変わりませんが、弔い上げの節目として、より大規模に行われます。
家族の代替わりが進んだなかで、長きにわたる供養の終わりを迎えるこの法要は、感謝の気持ちとともに故人を静かに送り出す場でもあります。
神式の葬式後の行事
仏教の法要と同じく、神道にも「霊祭(れいさい)」とよばれる葬式後の行事があります。
神道における葬式後の行事は、供養ではなく祭りとされており、故人の御霊を神として敬い、穏やかにまつることが目的です。
霊祭は、神社ではなく自宅や墓前などで執り行われることが多く、神職が祝詞を奏上し、ご家族が玉串を奉げて故人の御霊をまつります。
亡くなった日から50日が経過するまで、十日祭・二十日祭・三十日祭・四十日祭・五十日祭と、10日ごとに行われるのが特徴です。
なかでも五十日祭は、仏教でいう四十九日法要に相当し、忌明けの節目とされます。
近年は、10日ごとの霊祭を省略し、五十日祭のみを行うケースも一般的です。
また、五十日祭以降は、年ごとの命日に「式年祭(しきねんさい)」を行います。
一年祭・三年祭・五年祭などがあり、10年目以降は10年単位で続きます。
なお「供養」「成仏」「冥福」といった言葉は、仏教の用語です。
これらの言葉は神式の行事に適さないため、口にしないように注意しましょう。
法要の執り行い方
法要を滞りなく進めるには、事前の準備が欠かせません。
以下の6つのステップを意識することで、故人への敬意を示しましょう。
①日程と会場を決める
年忌法要は、本来故人の祥月命日に行うものですが、昨今は参列しやすい日程を優先して、命日の前後の土日に行うケースが増えています。
僧侶や参列者の都合、会場の空き状況などを考慮し、早めに調整を始めましょう。
菩提寺がない場合は、僧侶の手配サービスの利用もご検討ください。
②案内状を送付する
日程と会場が決まったら、参列者に案内状を送付します。
送付は法要の1か月前を目安に、往復はがきを利用したり返信用のはがきを添えたりして出欠の確認を取ると準備がスムーズに進みます。
封筒は白無地の一重封筒を選び、案内状には句読点を使わないのがマナーです。
③会食を手配する
法要後の会食は「お斎(おとき)」とよばれており、参列者への感謝を込めた場です。
案内状の返送が揃った段階で人数を確定し、会場や料理を予約しましょう。
最近は精進料理に限らずさまざまな献立が選ばれますが、祝い事を連想させる食材は避けるほうが無難です。
④引き出物を用意する
法要の参列者が帰宅する際には、お礼として引き出物を渡します。
海苔やお茶などの「消えもの」が好まれ、金額は2,000~5,000円ほどが相場です。
こちらも案内状の返送をもとに人数を確認しておくことで、適切な数を準備できます。
⑤お仏壇・お墓を掃除する
法要では、自宅の仏壇やお墓にお参りするのが一般的です。
僧侶や参列者が気持ちよくお参りできるよう、事前に掃除を済ませて、お花や線香、お供えを用意しておきましょう。
⑥お布施を準備する
僧侶を招く際に忘れてはならないのが、謝礼として渡す「お布施」です。
金額の相場は法要によって多少異なり、一周忌では3万~5万円、三回忌以降は1万~3万円が目安となります。
金額に明確な決まりはなく、地域や宗派によっても慣習が異なるため、不安がある場合は菩提寺や年長者に相談するとよいでしょう。
法事・法要当日の流れ

法事・法要当日の進行は、以下の通りです。
法事・法要当日の流れ
- 施主・ご家族・参列者の入場
- 開式の挨拶
- 僧侶の入場
- 僧侶による読経
- 焼香
- 僧侶による法話
- 僧侶の退場
- 閉式の挨拶
- 墓参り
- 会食
最初に施主やご家族、参列者が集まり、開式の挨拶を行います。
僧侶による読経が厳かに行われ、焼香で故人を偲んだのち、法話を通して仏教の教えや故人の生前の思い出が語られます。
閉式の挨拶をもって儀式は一区切りとなりますが、菩提寺で行う場合はその後に墓参りをするのが一般的です。
会食の席では、参列者同士が故人との思い出を語り合い、最後に施主が改めて感謝の言葉を述べて締めくくります。
施主は複数回挨拶する場面があるため、事前に内容を準備しておくと落ち着いて対応できるでしょう。全体を通して、感謝の気持ちをもって丁寧に進めることが、何よりの供養となります。
法事・法要のマナー

法事や法要に参列する際は、服装やお供え物などに気を配ることが大切です。
マナーを身につけたうえで、故人やご家族への思いやりをもって行動しましょう。
服装
法事・法要に適切な服装は、故人が亡くなってからの年数によって異なります。
三回忌までは、喪服の着用が基本です。
ご家族は正喪服か準喪服、参列者は準喪服を着用するのがふさわしいとされています。
三回忌を過ぎた頃からは、略喪服とよばれる控えめな服装に移行していくのが通例です。
ただし、年数を重ねるごとに法事・法要の儀礼的な要素は次第に簡素になり、身内だけで執り行うことも増えてきます。
そのため、過度に格式張る必要がない場合もありますが、服装に不安がある場合は、事前に施主やご家族に確認しておくと安心です。
お供え
参列の際に持参するお供え物は、故人への供養の気持ちを表す大切な品です。
お菓子や果物などの食べ物が選ばれることが多く、日持ちするものや個包装の商品が好まれます。
また、線香やろうそくといった仏事用の消耗品も、実用的で喜ばれるでしょう。
お供え物は、仏壇や祭壇に直接置くのではなく、玄関先でご家族に挨拶する際に「御仏前にお供えください」と添えて、袋から出して手渡すのが礼儀とされています。
些細な点にも配慮することで、故人とご家族への敬意を表せます。
法事・法要以外の行事

法事・法要のほかにも、葬式後にはさまざまな手続きや儀式が必要になります。
これらはご家族が感謝の気持ちや礼節を示す場でもあります。
葬式が終わったタイミングで慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
事務の引き継ぎ
葬式の事務は通常、世話役や葬儀社が中心となって進めますが、葬式後はご家族がその業務を引き継ぐ必要があります。
精進落としが終わったあとや、遅くとも翌日までには、香典帳や会葬者名簿、弔電、請求書などの書類を整理・確認しましょう。
特に金銭の出入りに関する情報はその場でしっかりとチェックすることが、後々のトラブル防止につながります。
支払い
葬式が終わると、関係各所に費用を支払わなければなりません。
葬儀社や仕出し店などから請求書が届いたら、内容を確認し、期日までに支払いを済ませましょう。
葬式費用は相続税の控除対象になるため、領収書はなくさないように、確実に保管してください。
なお、お寺へのお布施は葬儀の当日、または日を改めて訪問して渡すのが礼儀です。
挨拶周り
故人がお世話になった方々への挨拶回りも、葬式後に欠かせない行事の一つです。
世話役や故人の勤務先のもとに直接伺って、ご家族が感謝の言葉を述べます。
挨拶のタイミングは葬儀の翌日から初七日までが目安で、服装は地味な平服であれば問題ありません。
遠方の方や弔問に来られず、弔電や供花、香典を贈ってくれた方には、丁寧な礼状を送ることで感謝の気持ちを伝えられます。
位牌
位牌は、故人の霊魂が宿る場所とされる、大切な象徴です。
葬式後しばらくは「白木位牌」とよばれる仮の位牌を使用し、四十九日法要を過ぎると「本位牌」へと切り替えます。
白木位牌は法要後に菩提寺に納め、本位牌は僧侶が「魂入れ」を行ったのち、自宅の仏壇に安置するのが一般的です。
本位牌は故人1人につき1つが基本ですが、夫婦で連名にする場合や、複数の先祖を一つの位牌でまつる「繰出位牌(くりだしいはい)」を用いる場合もあります。
位牌は材質や仕上げにより価格に大きな差が生じるため、予算や宗派の習慣を考慮しながら選ぶとよいでしょう。
戒名
戒名は仏教において、故人が仏の弟子となったことを示す名前です。
宗派によって呼び方が異なる場合があり、たとえば浄土真宗では戒名ではなく「法名」とよばれます。
この世の名前を俗名だとすると、戒名や法名は「あの世の名前」だといえるでしょう。
どれだけ身分が高い人でも、戒名は基本的に2文字で表され、仏の世界ではすべての人が平等であることを示しています。
ただし、院号や道号などが加わると戒名の格式が高くなり、それに応じてお布施の金額には差が生じます。
仏壇・仏具
仏壇は、故人や先祖の霊を日常的に供養するための神聖な場所です。
新しく仏壇を用意する場合は、四十九日法要までに準備し、お坊さんに魂入れをしてもらうのが慣例となっています。
法要を重ねるたびにお参りする場所ですから、家庭の事情や宗派の習慣に合ったものを選びたいところです。
仏壇の種類は、大きく「塗り仏壇」「唐木仏壇」「家具調仏壇」の3つに分類されます。
塗り仏壇は、漆や金箔を用いた豪華な造りで、関西や東海地方で多くみられます。
関東地方で好まれる唐木仏壇は、黒檀や紫檀が使われており、傷がつきにくく耐久性に優れている点が特徴です。
最後に家具調仏壇は、現代的なインテリアに調和しやすく、洋室にも違和感なく置けるため、近年注目されています。
仏壇に必要な仏具としては、位牌やご本尊に加え、香炉と燭台、そして花立の「三具足」が基本です。さらに、正式な法要には燭台と花立をそれぞれもう1つずつ加えた「五具足」を揃えるのが望ましいとされています。
仏壇の設置場所については、仏間がない住まいも増えているため、扉の開閉スペースを含めた配置の工夫が必要です。
向きは北向きを避けるのが一般的で、神棚と同じ部屋に置く場合は、向かい合わないように配慮しましょう。
香典返し
香典返しとは、通夜や葬儀で香典をいただいた方への感謝の気持ちとして贈る品物のことです。
通常は四十九日法要を終えた忌明けの時期に、挨拶状とともに郵送します。
葬儀当日に即日返しを行う場合もありますが、高額の香典をいただいた場合は、後日改めて追加のお返しをするのがマナーです。
贈り物は、誰にでも使いやすく、あとに残らない消耗品が主流です。
お茶や海苔などが定番で、近年ではカタログギフトを利用して、受け取った方が自由に選べる形式も増えています。
また、金額はいただいた香典の3分の1から半分程度が相場です。
遠方の親族に対しては、交通費や宿泊費の負担を考慮して、少し多めにお返しする心遣いが求められます。
関連記事:会社への香典返しは必要? 辞退されたときの対応は?
納骨
納骨に決まった時期はありませんが、通常は四十九日や一周忌、三回忌といった節目に合わせて行われます。
最近では、葬儀当日にそのまま墓地へ移動し納骨を済ませるケースや、自宅で一定期間遺骨を安置するケースも増えています。
遠方からの親族の参加を考慮して、都合の良い日程に行うとよいでしょう。
納骨式では、僧侶に読経を依頼し、骨壷を墓に納め、生花や線香を供えたうえで焼香を行います。
なお、お寺の本堂で読経だけを済ませ、墓地には僧侶が同行しない場合もあります。
納骨には、火葬後に発行される火葬許可証が必要です。
また、遺骨を分けて手元供養していた場合は「分骨証明書」も欠かせません。
将来的に納骨する可能性がある場合には、あらかじめ証明書を取得しておくと安心です。
関連記事:最新の葬儀スタイル&お墓事情をご紹介!~樹木葬・海洋散骨・納骨堂
まとめ
本記事では、仏式の葬式のあとに執り行われる法事・法要について、その種類やマナーを解説しました。
ご家族や親族が集まる法事・法要の場では、故人を思う気持ちと同時に、正しい手順や礼節も重視されます。
地域や宗派によって異なる部分はありますが、このような行事ごとの節目を大切にし、丁重に故人を弔いましょう。
家族葬などの葬儀から家財整理、手元供養まで、ご葬儀・ご供養に不安がある方は、葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートにご相談ください。
藤沢・横浜・鎌倉で、ご家族の心に寄り添うご葬儀を提案いたします。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて