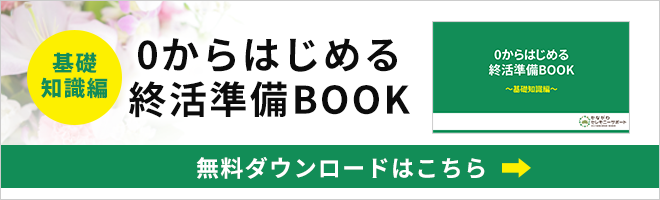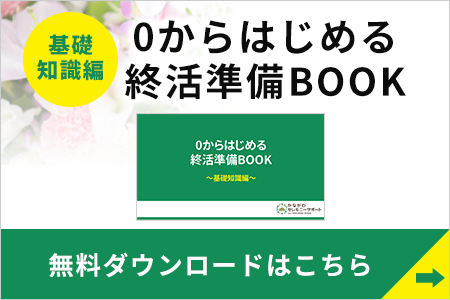葬儀の種類は何を選ぶ?種類ごとのメリット・デメリットを紹介
葬儀にはいくつかの種類があり、「どの葬儀を選んだらいいんだろう……」と悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
故人の遺志を汲み、ご家族にとって心残りのないお別れを迎えるためには、どのような葬儀があるのかを知っておくことが大切です。
そこで本記事では、代表的な葬儀の種類を、そのメリット・デメリットとともにお伝えします。
故人とご家族の希望を尊重し、納得のいく葬儀を執り行うために、ぜひ参考にしてください。
目次
葬儀の種類

それでは、葬儀にはどのような種類があるのかを見ていきましょう。
ここでは、一般的に広く知られている葬儀から、少々特殊な葬儀まで幅広くご紹介します。
葬儀の種類
・一般葬
・家族葬
・一日葬
・自宅葬
・直葬
・社葬
・合同葬
・無宗教葬
・生前葬
以下で、それぞれの特徴やメリット・デメリット、またどのような方に向いているのかをご確認ください。
一般葬の特徴
一般葬とは、参列者を限定しない葬儀のことです。
親族や友人、勤務先の関係者といった、故人やご家族と親交のあったさまざまな方が参列します。
大規模な葬儀となるため、主に葬儀場や寺院、神社などで執り行うのが特徴です。
なお一般葬では、2日間にわたってお通夜・葬儀・告別式・火葬が行われます。
一般葬のメリット・デメリット
一般葬のメリットは、故人と親交が深かった方やご家族と縁のある方など、多くの参列者にお見送りの機会を持っていただけることです。
一方で、ご家族は葬儀の準備や参列者の対応に追われる可能性がある点は、デメリットといえるかもしれません。
また大規模な葬儀となるため、会場費や飲食費、返礼品費といった費用の負担が大きくなることも考慮する必要があります。
一般葬に向いている方
故人の交友関係が広く、明るくにぎやかな場を好んでいた場合は一般葬が向いています。
多くの参列者を迎えて盛大な葬儀を執り行いたいご家族は、一般葬を選ぶとよいでしょう。
家族葬の特徴
ご家族や親族、また故人と親しかった友人など、限られた方だけで執り行う葬儀を家族葬といいます。一般葬と比べると参列者は少なく、気心の知れた方々のみでゆっくりと故人を偲ぶことができるのが特徴です。
家族葬の場合、一般葬のように大規模な会場である必要はなく、小規模な葬儀場や寺院、神社のほか、故人の自宅で執り行うケースもあります。
参列者の人数を考慮して、葬儀の規模に合った会場を用意するとよいでしょう。
関連記事:家族葬とは?小規模の葬儀を執り行うメリット・デメリットも
家族葬のメリット・デメリット
参列者は親しい間柄の方ばかりなので、余計な気を使わずに済み、故人との最後の時間を穏やかな気持ちで過ごせるのが家族葬のメリットです。
厳かな雰囲気のなか、故人との思い出をゆっくりと振り返ることができます。
とはいえ、参列者が限られる家族葬では、葬儀に参列できない方がいることも頭に入れておかねばなりません。
そういった方々への配慮を欠くと、あとからトラブルに発展する可能性がある点はデメリットといえます。
家族葬に向いている方
「身近な人だけで静かに故人を見送りたい」とお考えのご家族には、家族葬が向いています。
また、参列者が少ないことから一般葬よりも費用を抑えられるため、経済的な負担を軽減したい場合に選ばれています。
関連記事:家族葬はどこまでが呼ぶべき範囲?参列基準や参列時のマナーを紹介
一日葬の特徴
一日葬の特徴は、お通夜を省略して葬儀と告別式、火葬のみを1日で執り行うことです。
喪主が高齢で体力面に不安がある場合や、参列者のスケジュール調整が難しい場合など、なんらかの理由で葬儀を1日で終えたい場合に最適です。
参列者はご家族や親族、親しい友人などに限られるので、比較的小規模な葬儀になる傾向にあります。
また、一日葬は葬儀場で行われますが、法律によって故人が亡くなられてから24時間以内は火葬できないと定められているため、それまでご遺体を安置する場所が必要です。
ご自宅以外で安置する場合は、安置室を完備している葬儀場を選ぶとよいでしょう。
一日葬のメリット・デメリット
一日葬はお通夜がなく、1日で葬儀を終えるため、ご家族の体力的・精神的負担を減らせる点がメリットの一つです。
また、お通夜の会場費や飲食費などが不要となり、葬儀全体の費用を抑えられます。
反対に、故人とのお別れの時間が短くなる点はデメリットといえます。
ご家族や参列者のなかには、故人と向き合う時間を十分に取れずに、「心の整理が追い付かない……」という方が出てくるかもしれません。
さらに、菩提寺がある場合は、一日葬を執り行いたい旨を事前に住職に伝えて、許可を得る必要があります。
これは、お通夜・葬儀・告別式・火葬という一連の流れが、仏式の葬儀において宗教的な意味を持つためです。
一日葬に向いている方
参列者に高齢者や遠方に住む方が多い場合は、一日葬が適しています。
一日葬であれば、高齢者の体力的な負担を減らせるほか、遠方から参列する方のスケジュール調整が容易になります。
参列者の負担をできるだけ減らしたい場合には、一日葬を検討してみてはいかがでしょうか。
自宅葬の特徴
自宅葬は、故人の自宅で執り行う葬儀のことで、会場を借りる場合の葬儀と比べて自由度が高いのが特徴です。
たとえば、故人が生前好きだった食べ物や趣味で集めていた物を並べたり、よく聴いていた音楽を流したりすることも自由に行えます。
また一般葬や家族葬のように、参列者は喪服である必要はなく、故人とご家族の意向によってはカジュアルな服装での参列も可能です。
このようなアットホームな雰囲気で執り行う家族葬は、「住み慣れた我が家で見送られたい……」という故人の意向を尊重して選ばれることが多い傾向にあります。
自宅葬のメリット・デメリット
自宅葬では、会場費用が発生しない点は大きなメリットでしょう。
また、会場を借りる場合には時間が限られるのに対して、自宅葬であれば時間に融通が利くため、故人との最後のひとときをゆっくりと過ごせます。
一方、祭壇や棺などの手配は葬儀業者に依頼できますが、それ以外の準備や片付けはご家族が行う必要があり、ある程度の手間がかかる点はデメリットです。
こうした懸念を解消するには、親族や近所の方に協力を仰ぐ、または葬儀業者に葬儀全般のサポートを依頼して助力を得るのが有効です。
関連記事:自宅葬の費用相場はどれくらい?注意点や流れと共に解説
自宅葬に向いている方
自宅に十分なスペースがあり、故人と近しい間柄の親族や親しい友人など、少人数での葬儀を望んでいるご家族には、自宅葬が最適です。
また、「ペットと一緒に見送りたい」というご家族の希望がある場合も、自宅葬であれば問題なく葬儀を執り行うことができます。
直葬の特徴
直葬の最大の特徴は、お通夜や葬儀、告別式といった儀式を省略して火葬のみを行うことです。
参列者は招かず、ご家族や親族の数名のみが火葬場に集まり、そこでお別れを告げたのち、すぐに火葬するのが一般的です。
一般葬や家族葬などの場合は、故人をゆっくりと偲ぶ時間がありますが、直葬では故人との対面の時間は2時間程度と非常に短くなっています。
直葬のメリット・デメリット
直葬では、火葬以外の儀式をすべて省略しているため、一般的な葬儀であれば2日間を要する葬儀の時間を大幅に短縮することができます。
また、ご家族は葬儀や告別式などの準備や参列者への対応が不要になるほか、葬儀にかかる費用の負担を軽減できる点もメリットとして挙げられます。
その反面、簡略化した葬儀であるため、故人を偲ぶ時間が非常に短くなる点はデメリットでしょう。
最後のお別れに悔いが残る可能性もあるため、故人と縁の深かった親族や友人などには、直葬を執り行う旨を事前に伝えて理解を得ておく必要があります。
直葬に向いている方
葬儀や告別式などの儀式を省き、短時間で故人を見送れる直葬は、身体的な負担を抑えたい高齢者の方に向いています。
葬儀が長時間に及ぶことで、体力的な不安を感じている方は直葬を選ぶとよいでしょう。
また、葬儀費用を十分に用意できないご家族にとっても、火葬以外の儀式を省略する直葬であれば費用を抑えられるため、候補の一つになるのではないでしょうか。
社葬の特徴
社葬とは、企業の創業者や社長、役員など、経営に大きく貢献した方を対象とする葬儀のことです。
身内のみで葬儀を終えたのち、後日改めて企業関係者向けに執り行うのが特徴です。
多くの場合、企業が施主を、ご家族の代表が喪主を務めることになります。
葬儀の運営は企業側が担い、葬儀費用の全額、または一部を負担します。
一方、ご家族は喪主として、葬儀の場でのあいさつや受付の対応など、社葬全体の進行をサポートするのが一般的です。
社葬は故人の供養だけでなく、企業として故人の功績を称えるとともに、社外への信頼や評価を高めるという目的もあります。
社葬のメリット・デメリット
社葬にかかる費用は会社の経費として計上できるため、故人が所属していた企業にその費用を負担してもらえる点が大きなメリットです。
一方で、一部の企業では社葬に関する規定や方針が定められているため、ご家族は企業と相談しながら準備を進める必要があり、手間がかかる点はデメリットです。
社葬に向いている方
故人の事業発展への貢献度が高く、「企業として取引先や関係企業に弔意を示す必要がある」と判断された方には、社葬が適しています。
一般的には、創業者や社長をはじめとする役員が亡くなった際に社葬を執り行いますが、役職にかかわらず、業績向上に貢献した社員が対象となることもあります。
合同葬の特徴
ご家族と企業、もしくは複数の企業が合同で執り行う葬儀が合同葬です。
前項でお伝えした社葬と似ていますが、合同葬では身内のみの葬儀を行わず、ご家族と企業が費用や準備を分担して葬儀を執り行うといった点に違いがあります。
一般葬と社葬の要素を併せ持った葬儀、と捉えるとイメージしやすいかもしれません。
なお、合同葬では故人が勤めていた企業の関係者にくわえ、親族や友人などプライベートな関係者も参列するため、葬儀の規模が比較的大きくなります。
合同葬のメリット・デメリット
合同葬には、故人と縁の深かった方々に一度に参列してもらえるというメリットがあります。
多くの参列者が故人の思い出を語り合うことで、厳かな雰囲気のなかにも温かみのある葬儀となるでしょう。
しかし、ご家族は参列者の対応に手を取られるため、ゆっくりと故人を偲ぶことができない可能性があります。
「故人と最後に向き合う時間を十分に取りたい……」という方は、デメリットに感じるかもしれません。
合同葬に向いている方
故人が生前勤めていた企業で大きな功績を残し、さらに人望が厚く交友関係が広い場合は、合同葬が向いています。
「これまで仕事でお世話になった方や親しい方に、故人の旅立ちを見送ってほしい」と願うご家族は、合同葬を選ぶとよいでしょう。
無宗教葬の特徴
無宗教葬は、宗教の枠に捉われず、自由なかたちで故人を見送る葬儀のことを指します。
作法や葬儀の内容に制限がないため、故人とご家族の希望に沿ったオリジナルの葬儀を執り行えるのが無宗教葬の特徴です。
たとえば、葬儀中に故人の思い出を振り返るスライドショーを上映したり、参列者が手紙を読み上げたりといった内容を盛り込めば、ほかにはない特別な葬儀となります。
無宗教葬のメリット・デメリット
故人らしさを重視した、個性的な葬儀をあげられる点が無宗教葬の最大のメリットです。
また、特定の宗教に縛られないことから、僧侶や神主といった宗教者を呼ぶ必要はありません。
そのため、お布施や祭祀料などお礼の金銭も不要となり、葬儀にかかる費用を抑えることができます。
一方で、菩提寺がある場合、無宗教葬を行うと納骨を拒否されてしまう可能性がある点には注意が必要です。
仏教の教義として、読経や戒名なしの葬儀は供養として不十分であるとされるためです。
「納骨に関するトラブルを避けたい」とお考えのご家族は、仏式の葬儀を検討することをおすすめします。
無宗教葬に向いている方
宗教にこだわらず、独自の葬儀を行いたいご家族には無宗教葬が最適です。
無宗教葬であれば、形式に捉われず、故人のためだけの特別な葬儀にすることができます。
たとえば、故人の愛用品や思い出の品を展示すれば、思い出話に花が咲き、より温かみのある葬儀となるでしょう。
生前葬の特徴
生前葬とは、ご本人が亡くなる前に自ら喪主となって行う葬儀のことです。
一般的な葬儀とは異なり、ご本人がこれまでお世話になった友人・知人に直接会って、感謝の気持ちを伝えられるのが特徴です。
生前葬の内容に決まりはなく、宗教的な儀式を取り入れないケースが多くみられます。
そのため自由度が高く、ご本人の趣向を反映した個性的な内容の葬儀を執り行えます。
生前葬のメリット・デメリット
生前葬はご本人が喪主となって取り仕切ることから、参列者や葬儀の内容、開催日時などを自由に決められる点はメリットといえます。
ご本人の意向に沿って親交の深かった方々へ感謝の気持ちを伝えられるほか、これまでの人生を振り返るきっかけとなり、区切りをつけられるでしょう。
生前葬を行う場合、基本的に逝去後の葬儀は行いません。
しかし、「故人をしっかり見送りたい……」というご家族の意向がある場合は、改めて葬儀を執り行うこともあります。
つまり葬儀を2回行うことになり、ご家族や参列者の負担となる可能性があるため、事前によく相談・検討することが必要です。
生前葬に向いている方
持病が進行して余命宣告を受けており、亡くなる前にご自身の言葉で感謝の気持ちを伝えたいという方は、生前葬を選ぶとよいでしょう。
これまでお世話になった方と対面することで、自分自身の人生を振り返るきっかけにもなります。
また、人生の節目を迎えたときに親族で集まる機会をつくりたい方にも、生前葬が適しています。
葬儀の種類ごとの費用相場

ここまで葬儀の種類をお伝えしましたが、やはり気になるのはそれぞれの費用ではないでしょうか。
葬儀の種類ごとの費用相場を以下にまとめたので、ご参照ください。
葬儀の種類ごとの費用相場
| 葬儀の種類 | 費用相場 |
| 一般葬 | 100万~200万円程度 |
| 家族葬 | 30万~135万円程度 |
| 一日葬 | 40万~100万円程度 |
| 自宅葬 | 10万~100万円程度 |
| 直葬 | 20万~50万円程度 |
| 社葬 | 300万~2,000万円程度 |
| 合同葬 | 300万~1,000万円程度 |
| 無宗教葬 | 80万~200万円程度 |
| 生前葬 | 20万~150万円程度 |
上記の金額はあくまでも相場であり、必要な葬儀費用は参列者の数や会場の規模、葬儀の内容によって大きく変動します。
葬儀の種類を選ぶ際のポイント
葬儀の種類と、それぞれの費用相場を押さえたところで、ここからは葬儀の種類を決める際に意識しておきたい3つのポイントをお伝えします。
大切な方とのお別れの時間を悔いなく過ごすために、ぜひ参考にしてください。
ポイント①参列者の数で選ぶ
葬儀の種類を選ぶ際は、まず想定される参列者の人数を把握することが重要です。
故人の交友関係が広く、多くの参列者が見込まれる場合は、ご家族や親族だけではなく、友人・知人、会社関係者なども参列できる一般葬を選ぶとよいでしょう。
反対に参列者が少ないのであれば、家族葬や一日葬といった比較的規模が小さい葬儀が適しています。
ポイント②故人の意向を尊重して選ぶ
生前、故人から葬儀に関する要望を伝えられている場合は、その意向を尊重したうえで葬儀の種類を決めるのが望ましいでしょう。
「家族だけで見送ってほしい」「お世話になった人たちも呼んでほしい」など、故人が生前に具体的な希望を示すことは珍しくありません。
このような故人の気持ちを汲み取り、最適な葬儀の種類を選ぶことが大切です。
ポイント③予算で選ぶ
葬儀に充てられる予算を考慮することも、葬儀の種類を選ぶうえでは欠かせないポイントです。
葬儀の種類によって、必要な費用は大きく異なります。
「大人数で見送ってほしい」という故人の想いがあったとしても、葬儀費用が高くなりすぎて予算を超えてしまれば、その後のご家族の暮らしに影響を及ぼしかねません。
そのため、故人やご家族の希望を踏まえつつ、予算の範囲内で執り行える葬儀を選ぶことが大切です。
まとめ
今回は、葬儀の種類とそれぞれのメリット・デメリット、また向いている方の特徴をお伝えしました。
葬儀には、一般葬や家族葬をはじめ、いくつかの種類があります。
大切な方との最後の時間を悔いなく過ごすためには、故人やご家族の希望に合わせて最適な葬儀の種類を選ぶことが大切です。
その際、想定される参列者の人数や予算も考慮することで、無理なく葬儀を執り行えるでしょう。
神奈川県にお住まいで、葬儀に関するお悩みがある方は、葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートにご相談ください。
一般葬や家族葬をはじめ、さまざまな種類の葬儀を執り行えるほか、専任の担当者が故人やご家族の要望に沿った葬儀を実現いたします。
検討すれば、最適な葬儀を選ぶことができます。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて