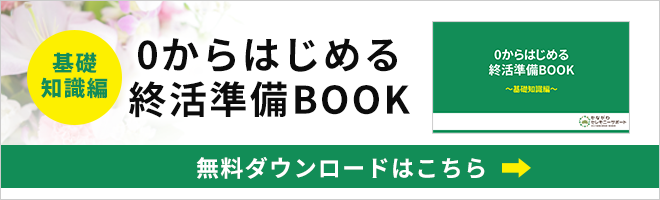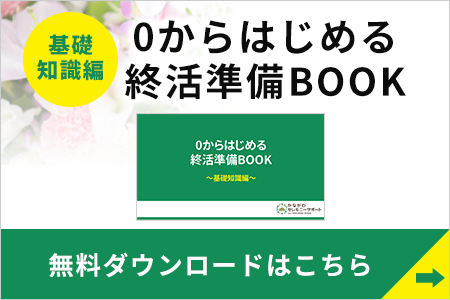葬儀費用の補助金はもらえる?支給対象や申請方法をわかりやすく解説
葬儀費用は突然の出費となり、遺族に大きな負担を与えることがあります。
そんな中、国や自治体、保険制度が用意する補助金を正しく理解しておくことはとても重要です。
制度を把握していれば、必要な手続きを落ち着いて進められ、経済的な不安を減らしながら故人を見送ることができます。
本記事では代表的な補助制度や申請方法、注意点を整理し、賢く活用するためのポイントを解説します。
葬儀費用を支援する補助金制度とは

葬儀費用は遺族にとって大きな負担となりますが、国や自治体、保険制度の補助金制度を理解しておくことが重要です。
事前にこれらを把握しておけば、万が一の際にも落ち着いて手続きを進められ、経済的負担を軽減しつつ故人を見送ることができます。
各制度の内容や金額、申請方法は異なるため、早めの情報収集が欠かせません。
関連記事:お葬式の平均相場はいくら?料金の内訳を形式別に解説
国民保険加入者への「葬祭費」
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、遺族は「葬祭費」を申請できます。
この制度は、葬儀費用の負担を軽減するもので、支給額は自治体によって異なりますが、一般的に1万円から7万円程度が支給されます。
申請は喪主や遺族が行い、故人の住んでいた市区町村役所に届け出る必要があります。
必要書類には死亡診断書、保険証、喪主名義の通帳などがあり、申請後、おおよそ1か月ほどで支給されます。
ただし、自治体ごとに手続きや必要書類が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
健康保険加入者への「埋葬料」「埋葬費」
会社員やその家族が加入する健康保険では、「埋葬料」が支給され、原則として一律5万円となります。
一方、国民健康保険の場合は「埋葬費」として支給され、金額は3万円から7万円程度が一般的です。
いずれも葬儀費用の一部を補助するもので、遺族にとっては心強い支援となります。
申請には死亡診断書や保険証が必要ですが、事前にこれらの書類を準備しておくと手続きがスムーズに進みます。
健康保険の「埋葬料」「埋葬費」は、葬儀費用に悩む遺族にとって、経済的な負担を軽減する大切な制度です。
労災保険からの「葬祭料」
仕事中や通勤途中の事故で亡くなった場合、労災保険から支給される「葬祭料」は、厚生労働省の労災保険給付基準に基づき、31万5,000円または「給付基礎日額の30日分」のいずれか多い額が支給されます。
実際の葬儀費用がそれ以上であっても、支給額の上限は変わりません。
この「葬祭料」は葬儀費用の一部を補助するための制度であり、遺族の経済的負担を軽減します。
申請は勤務先を通じて所轄の労働基準監督署に行い、必要書類には死亡診断書や葬儀費用の領収書が求められます。
生活保護受給者への「葬祭扶助」
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬儀費用をまかなえない遺族や身寄りのない方を対象に「葬祭扶助」が適用されます。
この制度は、市区町村が最低限の火葬費や遺体搬送費などを負担し、必要最低限の葬儀費用が補助されます。
豪華な葬儀や追加サービスは対象外となり、支給範囲は限られています。
申請は福祉事務所で行うことができますが、事前に相談しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
この制度は、生活保護受給者にとって大きな支援となるため、適切に利用することが重要です。
葬儀費用に対する補助金の割合について
葬儀費用に対する補助金の割合は、制度や保険によって異なります。
たとえば、国民健康保険の「葬祭費」は多くの自治体で5万円前後が支給され、健康保険の「埋葬料」も原則5万円が支給されます。
しかし、実際の葬儀費用は100万円を超えることが多いため、補助金だけでは不足することがあります。
また、生活保護の「葬祭扶助」は最低限の葬儀費用が支給され、上限があります。
これらの補助金は、葬儀費用全額を賄うものではなく、あくまで一部を補填するものです。
関連記事:葬儀費用はこわくない! その内訳をしっかり理解しよう
葬儀費用の補助金を申請する方法

葬儀費用の補助金を申請することは、遺族の経済的負担を軽減するために重要です。
申請先や必要書類、期限が異なるため、事前に理解しておくことが安心につながります。
各制度に対応した準備を行い、スムーズに手続きを進めるための流れや注意点を把握しておきましょう。
以下では具体的な流れや注意点を紹介します。
申請前に必要な手続き
葬儀費用の補助金を申請する前に、まず故人が加入していた保険制度を確認することが必要です。
国民健康保険、健康保険、労災保険、生活保護など、それぞれ申請先や必要書類が異なります。
どこに相談すればよいか分からない場合は、市区町村役場や勤務先の総務担当に問い合わせてみましょう。
さらに、死亡届の提出や保険証の返却など、基本的な手続きも忘れずに行いましょう。
これらを怠ると、申請ができない場合がありますので、事前にしっかり準備することが大切です。
申請に必要な書類と手順
補助金申請には、死亡診断書や火葬許可証、申請者の身分証明書などが必要です。
国民健康保険や健康保険では、被保険者証や葬儀費用の領収書が求められる場合もあるため、紛失しないよう注意しましょう。
申請手続きは、必要書類を揃えて申請先に提出し、内容確認後に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。
また、不備があると再提出を求められ、時間がかかることもあるため、チェックリストを用意してしっかり確認することが安心です。
正しい書類準備と手順の理解が、スムーズな申請につながります。
申請期限と振込までの期間
葬儀費用の補助金には申請期限が設けられており、通常「葬儀翌日から2年以内」となっています。
この期限を過ぎると補助金を受け取ることができなくなるため、早めに申請することが肝心でしょう。
申請から振込までの期間は自治体や保険組合によって異なり、一般的には1〜2ヶ月ほどかかります。
しかし、書類に不備があったり追加提出が求められると、さらに時間がかかることもあります。
必要書類をしっかり確認し、早めに手続きを行うことが、補助金を確実に受け取るためのポイントとなるでしょう。
申請者と申請先の確認
補助金を申請する際には、申請者と申請先を間違えないよう確認することが大切です。
国民健康保険の「葬祭費」は喪主や遺族が申請者となり、市区町村役所が窓口になります。
健康保険の「埋葬料」や「埋葬費」は、被保険者の家族が申請し、勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに届け出ます。
労災保険の「葬祭料」は、労働基準監督署が窓口となり、生活保護の「葬祭扶助」は福祉事務所で申請します。
それぞれの申請先を事前に把握しておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
関連記事:費用が安い葬儀はある?葬儀費用を抑えるポイントは?
補助金申請のポイントと注意点

補助金申請を行う際は、申請期限や必要書類の不備に注意が必要です。
一度の手続きで誤りがあると、補助金を受け取れない可能性があるため、事前に制度内容を確認しておくことが重要です。
また、制度ごとに申請先や条件が異なるため、しっかり準備しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
以下で、よくある注意点を詳しく解説します。
葬儀費用に含まれるものと含まれないもの
葬儀費用には、遺体搬送、棺や骨壺、祭壇、宗教者への謝礼、会場使用料、火葬料、遺影写真、人件費などが含まれます。
一方、香典返しや料理代、会葬礼状、返礼品、参列者の交通費や宿泊費、追加の装飾オプションは通常含まれません。
「どこまでが葬儀費用か分かりにくい」と感じることもありますが、補助金は基本的な葬儀運営に必要な費用のみが対象です。
補助金を利用する際には、対象と対象外を正しく区別し、無駄な出費を避けることが重要です。
費用の内訳をしっかり把握しておけば、補助金をより有効に活用できます。
補助金をもらえないケースとは
補助金を受けられないケースとして、まず故人が対象の保険や制度に未加入である場合があります。
たとえば、国民健康保険や社会保険に未加入の場合、葬祭費や埋葬料は支給されません。
また、申請期限を過ぎると権利を失うため、早めに手続きを行うことが求められます。
さらに、申請者が故人と同居していなかった場合や、必要書類に不備がある場合も審査が通らないことがあります。
補助金を受け取るためには、条件をよく確認し、書類を正確に提出することが大切です。
補助金が振り込まれるタイミング
補助金は申請後すぐに振り込まれるわけではなく、自治体や保険組合の審査を経て支給されます。
多くの場合、申請から1か月程度で振り込まれますが、書類に不備があるとさらに時間がかかることがあります。
また、申請が混雑している時期には、振込が遅れることも考えられます。
振り込みが遅れている場合は、自治体や保険組合に問い合わせて確認することが大切です。
支給時期を把握しておくことで、葬儀費用の支払い計画も立てやすくなります。
保険の資格喪失手続きの重要性
保険の資格喪失手続きは、補助金を受け取るための前提条件となるため、非常に重要です。
被保険者が亡くなった場合、資格は自動で消失しないため、遺族が速やかに役所や勤務先を通じて手続きを行う必要があります。
これを怠ると、葬祭費や埋葬料の申請ができなくなることがあります。
必要書類としては、保険証や死亡診断書などが求められます。
国民健康保険や社会保険では、この手続きが補助金申請の必須条件となるため、忘れずに行いましょう。
葬儀費用を抑えるための方法

葬儀費用を抑えるためには、補助金制度を活用するだけでなく、葬儀の規模やサービス内容を見直すことが重要です。
家族葬や直葬など小規模な形式を選ぶことで大きな節約が可能です。
また、市区町村の斎場を利用することで、数十万円単位の費用削減も期待できます。
以下で紹介する節約方法などを参考に、無理なく葬儀を進める方法を考えましょう。
葬儀の規模を小さくしオプションを控える
葬儀費用を抑えるための基本は、葬儀の規模を縮小し、オプションを最小限にすることです。
参列者を家族中心に絞った「家族葬」や、火葬のみを行う「直葬」を選べば、会場費や祭壇費、飲食代などの大きな出費を削減できます。
また、祭壇装飾や返礼品、会葬礼状などのオプションも、本当に必要なものに絞ることが重要です。
「どこまで削ってよいか」と不安になる方もいますが、希望や予算に合わせて柔軟に調整すれば問題ありません。
見積もりの際には細かく確認し、不要なサービスは遠慮なく断ることが、最も効率的な節約につながります。
自治体や加入保険の制度を活用する
自治体や加入している保険制度を活用することで、葬儀費用の負担を大幅に軽減できます。
多くの自治体では、国民健康保険や後期高齢者医療制度の「葬祭費」、健康保険の「埋葬料」などが補助として提供されています。
どこに相談すべきか分からない場合は、役所や保険組合の窓口で確認を行うことが第一歩です。
制度ごとに金額や申請方法が異なるため、公式ホームページや窓口で詳細を確認しておきましょう。
これらの制度を適切に活用すれば、想像以上に費用を抑えることができるかもしれません。
生活保護葬の利用
生活保護を受けている方には、「生活保護葬(葬祭扶助)」という制度があり、経済的に葬儀を行えない場合でも、必要最低限の葬儀費用が支給されます。
この制度は、火葬や搬送、基本的な祭壇などの費用をカバーしますが、豪華な祭壇や会食、返礼品などの追加サービスは対象外となります。
申請は福祉事務所で行うことができ、事前に相談を行うことで手続きをスムーズに進められるでしょう。
この制度は、経済的な不安を抱える方々にとって、葬儀費用の大きな支援となります。
関連記事:生活保護受給者でも葬儀はできる!鎌倉市の生活保護葬について解説
まとめ:葬儀費用を賢く抑える補助金活用のポイント
葬儀費用を抑えるためには、補助金制度を理解し、早めに準備を始めることが欠かせません。
国民健康保険の「葬祭費」や健康保険の「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護葬の「葬祭扶助」など、状況に応じた制度を活用することが大切です。
申請期限や必要書類に不備があると補助金を受け取れないため、事前確認と相談を徹底しましょう。
補助金を上手に活用し、不要なオプションを控える工夫をすれば、無理なく葬儀を進めることができます。
費用を抑えつつ、故人を心を込めて見送るための最良の方法を選びましょう。
葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートでは、葬儀費用や補助金制度に関するご相談にも対応しております。
制度の活用方法や費用を抑える工夫について、経験豊富なスタッフが分かりやすくご案内いたします。
安心してご葬儀を迎えるために、ぜひ一度ご相談ください。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて