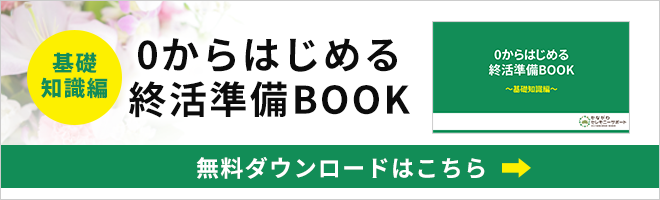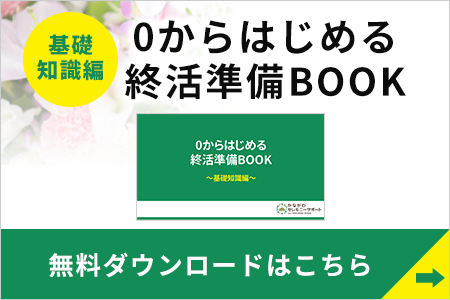葬式をしない場合に選ばれる直葬の特徴を徹底解説
近年、葬儀の準備や費用の負担を抑えるために、葬式をしないご家族が増えています。
とはいえ、「葬式を行わない場合、どのように故人を見送ればいいのかわからない……」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、葬式をしない場合の選択肢である「直葬」について解説します。
葬式を省いたお見送りの方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
葬式をしないとどうなる?

葬式は法律によって義務づけられているわけではないため、執り行わなくても違法になることはありません。
ただし、近親者が亡くなった際には、役所への死亡届の提出と、火葬または土葬の手続きが必要です。
死亡届は、故人の死亡を知った日から7日以内に、役所へ提出しなければなりません。
また、死後24時間以上経過してから火葬を行うことが、法律で定められています。
なお、土葬は許可された地域以外で行うと法律に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
葬式をしないという選択自体は問題ありませんが、死亡届の提出と火葬・土葬を行わないと、法律違反になってしまうことを覚えておきましょう。
葬式をしない場合に選ばれる直葬(火葬式)とは

直葬とは、一般的な葬式を簡略化した葬儀形式のことで、火葬式や密葬ともよばれます。
ご家族や親族、故人が親しくしていた友人などを参列者として招いて、少人数で行われることが一般的です。
直葬では、お通夜や告別式などを行わずに、ご遺体を火葬場に直接運び、火葬のみで弔います。
読経供養などを行わないため、宗教儀式を執り行う式場や祭壇は必要ありません。
関連記事:直葬(火葬式)ってなに?費用~準備、特長、注意点を解説します!
直葬が選ばれる理由
直葬が選ばれている背景には、以下のような理由があります。
直葬が選ばれる理由
・理由①費用を抑えられるため
・理由②最小限の人数で見送ることができるため
・理由③故人の意思を尊重するため
・理由④葬式に呼べる人数が限られているため
・理由⑤葬式の形式にこだわりがないため
理由①費用を抑えられるため
直葬が選ばれる理由として、費用を抑えられる点が挙げられます。
葬式を行う場合、参列者への接待費用や式場・祭壇の使用料、また僧侶へのお布施といった費用が必要です。
一方でお通夜や告別式を省く直葬では、上記のような費用はかからないため、葬儀費用を大幅に抑えられます。
関連記事:葬儀の見積もりの取り方とは?費用の内訳と比較時のポイントを解説
理由②最小限の人数で見送ることができるため
故人を最小限の人数で見送りたい場合も、直葬が選ばれています。
お通夜や告別式を行う場合、血縁者はもちろん、友人や会社関係者など、多くの方が参列するのが一般的です。
しかし、葬式の参列者が多くなればなるほど、葬儀の準備や参列者の対応に追われて、ご家族の精神的な負担も大きくなります。
そのため、ご家族の精神的な負担を軽減する目的で、小規模な直葬が選ばれることもあるのです。
理由③故人の意思を尊重するため
故人が生前に、「自分の葬式はしなくてよい」「火葬だけで問題ない」と話していたのであれば、その意思を尊重して直葬を選ぶ場合もあります。
生前の発言や遺言状などから、故人の意向を尊重することも大切です。
理由④葬式に呼べる人数が限られているため
参列者の人数が少ない場合も、直葬が選択肢として挙げられます。
故人が高齢で親しい友人が少ない、または身寄りがない場合は、お通夜や告別式のない直葬が選ばれることがあるのです。
理由⑤葬式の形式にこだわりがないため
葬式の形式にこだわりがないことを理由に、直葬を選ぶ方も少なくありません。
葬式は本来、宗教的な儀式として故人の成仏・ご冥福を祈るものです。
しかし、近年では宗教に対する価値観の変化や多様化によって、伝統的な形式の葬式を望まない方もいらっしゃいます。
そのような考えをもつ方にとって、宗教的な儀式を行わない直葬は、新たな選択肢の一つとなっているのです。
直葬を執り行う際の注意点

「費用を安く抑えたい」「少人数で見送りたい」というご家族には、直葬が向いています。
直葬を執り行う際には、以下のような注意点があります。
直葬を執り行う際の注意点
・注意点①ご遺体を安置する場所が必要になる
・注意点②故人とのお別れの時間が短くなる
・注意点③弔問に対応する必要がある
・注意点④親族に理解してもらえない可能性がある
・注意点⑤菩提寺とトラブルになる可能性がある
注意点①ご遺体を安置する場所が必要になる
直葬の場合も、ご遺体を安置する場所を用意しなければならない点に注意が必要です。
日本の法律では、死亡診断を受けてから24時間以内は火葬が禁止されています。
そのため、火葬を行う日まで、ご遺体を安置する場所を確保する必要があります。
故人が自宅で亡くなったのであれば、自宅で安置することも可能です。
しかし、病院や老人ホームといった施設で亡くなったときは、一般的に火葬場の安置室を利用することになります。
そのため、葬式をしない場合でも、安置室の確保やそれに伴う料金は必要です。
注意点②故人とのお別れの時間が短くなる
直葬ではお通夜や告別式がなく、火葬までの時間が短縮されてしまうため、故人とお別れする時間が短くなる点にも注意してください。
葬式は故人との最後の時間を過ごす場でもあるため、お通夜や告別式のない直葬を選んだとしても後悔しないかどうかを、十分に考慮することが大切です。
注意点③弔問に対応する必要がある
直葬を執り行った際、火葬後に逝去の知らせを受けた方が、弔問に訪れることもあるかもしれません。
そのときには、弔問客への対応が必要になり、ご家族の負担が大きくなってしまうことも考えられます。
そのため、故人と関わりがあった方に逝去を知らせる際は、生前のお礼にくわえて、しばらくのあいだは弔問を控えてほしい旨を伝えるとよいでしょう。
注意点④親族に理解してもらえない可能性がある
直葬の選択が、親族に理解されない可能性がある点にも注意が必要です。
親族のなかには、「伝統的な葬式を行うのが当たり前」「お通夜や告別式など、お別れの時間を大事にしたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
そういった価値観をもつ方々に相談もなく直葬を選んでしまうと、理解を得られない可能性があります。
直葬を執り行う場合は、故人の意向に沿って直葬を選択することを親族や参列希望者に伝え、納得してもらうことが重要です。
注意点⑤菩提寺とトラブルになる可能性がある
宗教的な儀式を行わない直葬を選ぶことで、先祖代々お世話になっている菩提寺とトラブルになる可能性もあります。
一般的に、菩提寺の僧侶が葬儀中の宗教儀式を執り行い、葬儀後にはそのお寺のお墓に納骨します。
しかし、宗教的な儀式を行わない直葬では、菩提寺が納骨を断る場合があるのです。
菩提寺をお持ちであれば、直葬を行う旨を事前に相談することをおすすめします。
遺言書に「葬式をしないように」と書いてあった場合はどうする?

故人が遺言書に「葬式はしないでほしい」といった内容を記述していたときは、どのように対応したらよいのでしょうか。
この項では、遺言書の法律的な効力に関して解説します。
法律的な効力の有無
遺言書における「葬儀は必要ない」という内容は、故人の感情的な希望であるため、法律的な強制力はありません。
故人の意思として尊重することが大切ですが、葬儀の可否に関しては、最終的にご家族が決定します。
法律的な効力がある項目
遺言において、法律的な効力があるのは、以下のような項目に限ります。
法律的な効力がある項目
・認知
・遺贈と寄付行為
・後見人、後見監督人の指定
・相続の廃除およびその取消
・相続分の指定または指定の委託
・遺産分割方法の指定または指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
・遺言執行者の指定または指定の委託
・遺贈減殺方法の指定
遺言書には願いを自由に書くことができますが、上記以外の事柄については、法律上の強制力はありません。
直葬の流れ
直葬が選ばれる理由や注意点を押さえたところで、直葬の具体的な流れについても把握しておきましょう。
以下に、直葬の全体の流れをまとめました。
直葬の流れ
- 臨終・お迎え(ご遺体の搬送)
- ご遺体の安置
- 納棺
- 出棺・火葬場への搬送
- 火葬
- お骨上げ(収骨)
医師によって故人の死亡が確認されたあとは、故人の近親者・友人にその旨を伝えるのと同時に、葬儀社への速やかな連絡も必要です。
葬儀社の担当者が到着したあとは、ご遺体を寝台車に乗せて、葬儀社や火葬場に併設された安置場所まで搬送してもらいます。
そのあとに行うのは、故人のご遺体を清めて身支度を整えてから、お花や想い出の品と一緒に棺に納める、納棺の儀式です。
納棺後は、ご遺体を火葬場へ搬送し、火葬を見届けます。
滞りなく火葬を終えたら、お骨上げ(収骨)を行い、最後にお骨と埋火葬許可証を受け取ります。
関連記事:葬儀なしで火葬のみを行うことは可能?流れや費用相場は?
直葬の費用相場
直葬の費用相場は、20万~40万円程度といわれています。
一般的な葬式の費用相場が110万~200万円程度といわれているため、直葬を選ぶことで費用を大幅に抑えられます。
直葬を選んだ際の費用の内訳を、以下で見ていきましょう。
直葬の費用の内訳
・搬送サービス料(病院から安置所・安置所から火葬場)
・安置施設使用料(大抵は3日分)
・ドライアイス代(大抵は3日分)
・棺、骨壺、花などの物品代
・火葬料
・スタッフの人件費
・火葬手続き代行の費用
上記のうち、安置施設使用料とドライアイスに関しては、4日分以上を希望する場合、追加料金が必要になる可能性があります。
なお、故人のご家族が生活保護を受けている、また故人に扶養義務者がおらずご家族以外の方が対応するなどのケースでは、葬祭扶助の利用によって約20万円を支給してもらえます。
これは直葬に必要な費用とほぼ同等であるため、この制度を利用して故人の直葬を行うことが可能です。
なお、直葬の費用は葬儀社のプランやサービスによって異なるため、あらかじめ見積もりを依頼することをおすすめします。
葬式もお墓も不要の場合
直葬でも、お墓を用意するのが一般的です。
しかし、故人の意思や金銭的な問題から、「葬式もお墓も必要ない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときは、以下のような選択肢がありますので、参考にしてください。
葬式もお墓も不要な場合の選択肢
・散骨する
・永代供養墓を利用する
・樹木葬を行う
散骨する
お墓を用意しない選択肢として、散骨が挙げられます。
散骨とは、遺骨を粉状にしたのちに、空や海、山などにまいて供養する方法です。
近年では、遺骨を入れたカプセルを宇宙に飛ばす、宇宙葬も登場しています。
散骨には、全部散骨と一部の遺灰を残す一部散骨があります。
「故人の意思で散骨するが、遺灰のすべてをまいてしまうのは忍びない……」とお考えの方には、一部散骨がおすすめです。
ただし、散骨での供養が許されているのは、粉状にした遺骨のみである点に注意が必要です。
遺骨をそのままの状態で放置してしまうと、法律に抵触する恐れがあります。
また、条例で散骨が禁止されている場所もあるため、散骨を検討する際は、葬儀社へ事前に相談しておくことが大切です。
関連記事:海洋散骨とは?海に散骨する方法や費用相場、注意点を徹底解説
永代供養墓を利用する
遺骨を永代供養墓に預けるのも、一つの方法です。
永代供養墓とは、ご家族に代わり、寺院や霊園が遺骨を管理する形式のお墓です。
お墓は複数の遺骨をまとめて埋葬する「合祀墓(ごうしぼ)」になり、仏壇式やロッカー式、また機械式など、さまざまな種類が存在します。
継承者がいない方や身寄りのない方、また菩提寺を持たない方が亡くなった場合は、永代供養墓が選ばれることが多くあります。
また、「お墓の費用などで、家族に負担をかけたくない」と考える方が、自身の終活中に永代供養墓を希望することも珍しくありません。
樹木葬を行う
お墓を用意しない場合、樹木葬という選択肢もあります。
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や花を墓標にして弔う埋葬の方法です。
桜やハナミズキなどのシンボルツリーの周りに遺骨を埋葬する形式や、草花や芝生で彩るガーデン風、バラをシンボルとする英国庭園風など、さまざまな樹木葬があります。
宗教や宗派の影響を受けない樹木葬では、血縁関係や婚姻関係にない大切な人やペットと一緒に埋葬してもらうことができます。
墓石が必要ないため、費用を抑えられる点もメリットといえるでしょう。
まとめ
本記事では、葬式をしない選択肢として選ばれる直葬について解説しました。
葬儀の準備や費用の不安を抑えられることから、直葬を選ぶ方が増えています。
ただし、直葬の場合でもご遺体の安置場所が必要になる点や、故人とお別れする時間が短くなる点などに注意しましょう。
葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートでは、故人の意向やご家族の想いに寄り添い、大切な方との最後のお時間を心置きなく過ごしていただくためのお手伝いをしています。
直葬に関する疑問や不安がある方も、気軽にご相談ください。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて