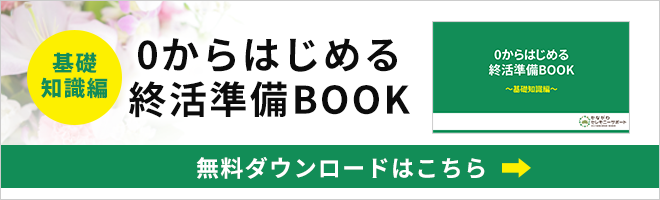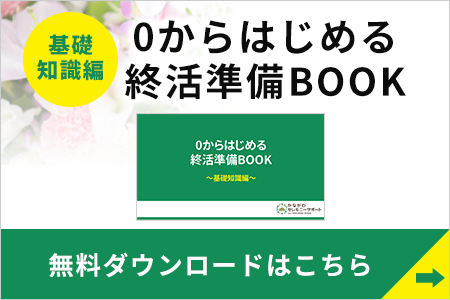葬式と通夜・告別式の違いとは?それぞれの流れや日程を解説
葬式を構成する「通夜」と「葬儀・告別式」は、故人と最後の時間を過ごす大切な儀式です。
しかし、実際に身内に不幸があった際に、ご家族としてどのような葬式にすればよいか、迷ってしまうかもしれません。
そこで本記事では、通夜と葬儀・告別式の異なる点を確認したうえで、それぞれの流れを紹介します。
各儀式を滞りなく執り行い、大切な別れの時を悔いなく過ごすために、最後までご覧ください。
目次
葬式の儀式の違い

葬式とは、通夜や葬儀、告別式といった、いくつかの儀式を含む言葉です。
各儀式は、目的や日程、参列者などに違いがみられますが、これらを正しく認識できていない方もいるかもしれません。
突然の訃報に慌てないためにも、それぞれの違いを理解しておきましょう。
通夜
通夜は、故人と生前親しかった人たちが集まり、最後の夜を共に過ごしながら別れを惜しむ儀式です。
もともとは、自宅で故人とともに最後の夜を過ごすことが一般的でしたが、現在では会館や斎場で行われる「半通夜」が一般的になっています。
この場合、儀式の所要時間は2~3時間程度と比較的短時間で終了します。
通夜の主な流れとしては、僧侶による読経や焼香、法話などが行われることが多く、宗教や地域の風習により内容はさまざまです。
通夜は、ご家族や親族だけでなく、故人と親しかった友人や知人などが参列する場であり、しめやかな雰囲気のなかで故人を偲ぶ時間となります。
葬儀・告別式
通夜の翌日に行われるのが、葬儀および告別式です。
葬儀は、故人の冥福を祈り、その魂を静かに見送るための宗教的な儀式です。
僧侶による読経や焼香、弔辞などが行われ、近親者が中心となって参列します。
葬儀の直後に行われる告別式は、友人や知人、会社関係者など、広い範囲の人々が故人に最後の別れを告げるための儀式です。
もともと葬儀と告別式は別々に行われていましたが、近年ではこの2つを一体化して行うケースが増えており、その場合は一括りに「告別式」とよばれることがあります。
告別式は出棺前の最後の儀式となるため、参列する場合は開始時間よりも早めに到着しておくのがマナーとされています。
通夜と葬儀・告別式の違い

このように、通夜と葬儀・告別式は役割が異なります。
次に、両者のより細かな違いを項目別に見ていきましょう。
目的
通夜の目的は、故人との最後の夜を共に過ごし、別れを惜しむことにあります。
ご家族や親しい人たちが集まり、生前の思い出を語り合いながら、静かに故人を偲ぶ時間です。
一方で、葬儀・告別式の主な目的は、故人の霊を供養し、正式に別れを告げて送り出すことです。
宗教的な儀式としての意味合いが強く、故人の旅立ちを見守る厳粛な場といえるでしょう。
関連記事:葬儀・葬式の流れとは?ご逝去から葬儀までの手順・段取りを徹底解説
日程
通夜は、故人が亡くなってすぐに、葬儀の前日の夕方から夜にかけて行います。
時間帯としては18~20時頃が目安とされており、仕事帰りに参列できるよう配慮します。
葬儀・告別式は、通夜の翌日に実施するのが一般的で、午前中から正午に執り行われることがほとんどです。
火葬場の予約状況や地域の事情により、午後になる場合もありますが、いずれも日中に行うのが基本です。
参列者
通夜には、ご家族や親族に加え、故人と特に親しかった友人や関係者が集まる一方で、葬儀・告別式には、より広範な関係者が参列します。
ご家族や親族はもちろん、知人や会社関係者、仕事の取引先など、故人に縁の合ったさまざまな人々が集まり、最後の別れを告げるのです。
通夜に参列した場合は葬儀にも参列することが基本ですが、都合がつかない場合は、どちらかのみに参列しても問題ありません。
知人や会社関係者であれば、葬儀のみに参列するのが一般的です。
内容
通夜では、僧侶による読経や焼香が行われるほか、参列者が故人のご遺体のそばで静かに過ごすのが伝統です。
「通夜振る舞い」とよばれる食事の場を設けることもあり、故人を偲びながら食卓を囲む風習が今も受け継がれています。
一方、葬儀・告別式では、読経や焼香にくわえて、故人への弔辞の朗読や棺への花入れ、最後の別れの挨拶などが行われます。
服装
通夜も葬儀・告別式も、基本的には喪服で参列するのがマナーです。
ただし、通夜に関しては、急な知らせに駆けつけるという性質もあるため、最近では黒や紺などの控えめな色味の平服で参列することも受け入れられています。
一方、葬儀・告別式では、格式を重んじた正式な喪服で参列します。
男性はブラックスーツに黒ネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツが望ましく、光沢のある素材や華美なアクセサリーは避けなければなりません。
通夜の流れ

繰り返しになりますが、通夜は故人と最後の夜を過ごす大切な儀式です。
ここからは初めて経験する方でも安心して臨めるように、訃報の連絡から通夜振る舞いまでの一連の流れについて紹介します。
①訃報の連絡
身内の方が亡くなったら、まずは近親者や親しい関係者へ早急に連絡します。
そのうえで、通夜と葬儀の詳細が決まった段階で、正式な案内を行いましょう。
連絡は電話が基本ですが、誤解を防ぐために日時などの詳細は文書やメールで補足すると丁寧です。
SNSは情報の届き方にばらつきがあるうえ、快く思われない場合があるため、訃報の伝達手段としては控えるのが無難です。
関連記事:訃報を受けたときにするべきこととは?
②納棺
通夜の前には、故人の遺体を整え、白装束を着せたうえで棺に納める「納棺」が行われます。
近年では、納棺師や葬儀社のスタッフが作業を行うのが一般的になってきていますが、ご家族が立ち会い、思い出の品や手紙を一緒に入れることも可能です。
納棺に間に合わなかった場合でも、出棺前に故人に贈りたいものを納める時間が設けられることが多いため、準備しておくとよいでしょう。
③供花
供花(くげ/きょうか)とは、故人に備える花のことです。
主に近親者や友人、会社関係者などから、祭壇を美しく飾る目的で贈られます。
並び順には一定の配慮が必要で、基本的には血縁者などの故人に近しい人から順に、関係性に応じて並べられます。
葬儀社が適切に調整してくれるので、不安な場合は相談するとよいでしょう。
④返礼品の確認
香典をいただいた方への返礼品の準備も欠かせません。
昨今では、後日送るのではなく、当日に渡す「即日返礼」が主流となりつつあります。
そのため、あらかじめ品物を袋に入れて、受付でスムーズに渡せるように準備しておくと安心です。
高額な香典をいただいた場合は、後日改めてお礼の品を贈るのがマナーとされています。
⑤僧侶へのお布施
通夜では、僧侶による読経や法話が行われます。
菩提寺がある場合は、早めに連絡を取り、通夜や葬儀の日程に関する相談とともに、お布施の準備も進めます。
お布施は通夜の始まる前に、控室などで直接手渡すのが一般的です。
宗派や地域によって習慣が異なる場合もあるので、不明な点は葬儀社に確認するとよいでしょう。
⑥受付
通夜の30分ほど前に、受付が始まります。
受付係は、参列者からの香典を受け取り、芳名帳への記帳を案内する役割を担います。
ご家族が務めるのではなく、信頼できる知人や近隣の方にお願いするのが慣例です。
受付係には、参列者からお悔やみの言葉を受けた際、丁寧にお礼を述べるように伝えておくことが大切です。
⑦通夜
通夜では、僧侶による読経と参列者による焼香が中心となります。
焼香の順番は、喪主から始まり、ご家族や親族、そして一般参列者へと続きます。
焼香のあとに僧侶による法話がある場合は、静かに耳を傾けましょう。
⑧通夜振る舞い
通夜のあとの通夜振る舞いは、参列者への感謝を込めた食事の席です。
時間にして1~2時間程度で、喪主やご家族が参列者に直接お礼を伝えたり、思い出を語り合ったりする場になります。
また、食事の終わり頃には翌日の葬儀の案内を簡単に伝えておくと親切です。
僧侶にも食事を用意しますが、辞退されることも多いので、そのときのために食事の代わりとなる「お膳料」を用意しておきましょう。
葬儀・告別式の流れ

通夜の翌日には、葬儀・告別式が行われます。
準備から焼香、香典返しに至るまでの一連の流れを、順を追って解説します。
①準備
葬儀・告別式は通常、通夜を終えた翌日に同じ会場で執り行われることが多く、設備もそのまま使用するケースが一般的です。
ただし、自宅で通夜を行い、斎場で葬儀を行う場合には、会場の移動や設営の段取りが必要になります。
全体の進行については、葬儀社と密に打ち合わせを行うことが大切です。
葬儀・告別式のあとは火葬場へと向かうため、当日の移動計画や車の手配も事前に確認しておきましょう。
②受付
葬儀・告別式の受付は、式が始まる30分ほど前に開始します。
受付では、参列者から香典を受け取り、芳名帳に記帳してもらいます。
ご家族が直接対応するのは難しいため、信頼できる知人や会社関係者に受付係や世話役を依頼しておくと安心です。
香典の取り扱いには十分注意し、参列者ごとの名前や金額がわかるように、しっかりと管理しましょう。
③葬儀開始
開始時刻になると、僧侶が式場に入場し、読経が始まります。
会場内では、祭壇に向かって右側に親族、左側に友人や知人、会社関係者が座るのが主流です。
僧侶が入場する際には、静かに合掌し、黙礼をもって迎えましょう。
読経の時間は宗派によって異なりますが、30分から1時間程度が目安です。
読経中には故人に戒名が授けられる場合もあり、冥福を祈る時間となります。
④弔辞
読経の途中や終了後、故人と縁の深い方による弔辞が行われます。
事前に喪主からお願いしておくことが多く、友人や恩師、職場の上司などが務めるのがふさわしいでしょう。
葬儀社の進行係から紹介されたのち、弔辞を述べる方が祭壇の前へ進み、故人への想いを言葉にして伝えます。
読み終えた弔辞文は、祭壇の前に供えるのが慣例です。
弔電が多く寄せられた場合は、そのなかから数通が奉読され、残りは差出人の名前のみ読み上げることもあります。
⑤焼香
弔辞や弔電のあと、再び僧侶による読経が始まり、焼香を行います。
焼香は、故人への敬意と冥福を祈るための大切な行為です。
方法は宗派によって異なりますが、何より大切なのは心を込めて手を合わせる姿勢です。
焼香の順番は、喪主、ご家族、親族、そして一般の参列者が続くかたちで進みます。
なお、一般の参列者による焼香以降の儀式が「告別式」という位置づけです。
⑥香典返し
香典返しとは、参列者からの香典へのお礼として贈る品物のことです。
かつては四十九日法要のあとに送付するのが通例でしたが、先述の通り、近年は当日に返礼品を渡す「即日返礼」が主流となっています。
この場合、香典の金額にかかわらず同じ品を全員にお渡しします。
返礼品は手提げ袋に入れて、受け取りやすくしておくのがマナーです。
葬式の日程はどのように決める?
葬儀の日程を決める流れについて、事前に把握しておくことは非常に大切です。
その場面が訪れたときには、突然の別れに戸惑うなかで、関係者との調整や手配を迅速に行わなければなりません。
まず、故人のご遺体を安置したあとに、葬儀社とご家族が集まって打ち合わせを行います。
深夜や早朝に亡くなられた場合は、翌日以降に話し合いの時間を設けることもあります。
日程を決めるのは、喪主を中心としたご家族や菩提寺の僧侶、そして葬儀を取り仕切る葬儀社の三者です。
実際は、経験のある葬儀社の担当者が進行をリードしながら、斎場や火葬場の空き状況、僧侶の都合などを考慮して最適な日程を提案してくれることが一般的です。
通例では、故人が亡くなった翌日に通夜、その翌日に葬儀・告別式と火葬が行われます。
ただし、これはあくまで目安であり、地域の習慣や六曜(仏滅など)、参列者の都合などによって調整が必要になる場合もあります。
特に、人口が多い都市部の斎場や火葬場では、予約が取りづらく、数日先の日程になることも珍しくありません。
また、日程が決まったあとは、親族や関係者に故人の訃報を知らせます。
その際には、故人の名前や葬儀の日時・場所、喪主の名前、葬儀の形式(仏式・神式・無宗教など)を正確に伝えることが大切です。
葬儀の日程を決める際の注意点
葬儀の日程を決める際には、喪主やご家族だけでなく、関係各所との調整も必要です。
参列者や関係者の負担を軽減し、葬儀を円滑に執り行うためにも、慎重なスケジューリングが求められます。
特に火葬場や僧侶といった式に欠かせない関係先については、早めに確認を取っておくことが大切です。
以下に、日程を決める際に押さえておきたい具体的なポイントを紹介します。
火葬場の空き状況を確認する
葬儀の日程を決めるうえでもっとも重要となるのが、火葬場の予約状況です。
近年、火葬場は混雑する傾向があり、希望日に空きがないことも少なくありません。
通夜や葬儀の日時を先に決めてしまった場合、火葬の予約が取れずにスケジュール全体を変更せざるを得なくなることもあります。
そのため、まずは火葬場の空き状況を確認し、それに合わせて葬儀の日取りを調整するのが現実的です。
葬儀・告別式・火葬を同日中に行えるよう調整することで、参列者の移動や滞在の負担軽減にもつながります。
僧侶の都合を確認する
葬儀を執り行う際には、僧侶の出席が不可欠です。
特に、古くからお付き合いのある菩提寺に依頼する場合には、必ず事前に僧侶のスケジュールを確認しておきましょう。
こちらの都合で日程を確定してから連絡を入れると、僧侶の都合がつかずに再調整が必要になる場合があります。
その際、日程を数日ずらすか、同じ宗派の僧侶を紹介してもらうという選択肢もありますが、円滑な進行のためには、なるべく早い段階で相談しておくのが賢明です。
まとめ
本記事では、葬式に含まれる通夜と葬儀・告別式を比較し、違いを紹介しました。
親しい人たちが最後の夜を過ごす通夜に対し、葬儀・告別式は、より厳かな雰囲気のなかで、故人に別れを告げてお見送りする儀式です。
通夜には、ご家族や親族が集まり、葬儀・告別式には、知人や会社関係者など、より広い関係者が参列します。
葬儀の日程は、事前に火葬場や僧侶のスケジュールも確認したうえで決定し、親族や知人に連絡しましょう。
段取りや費用に不安がある方は、葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートにご相談ください。
スタッフが24時間待機しておりますので、葬儀社を急いでお探しの方は、時間帯を問わずにお問い合わせが可能です。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて