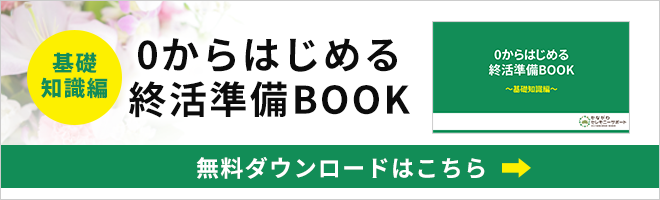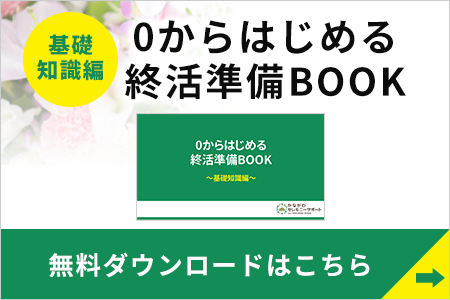葬儀にかかる時間はどのくらい?日程と流れを紹介
葬儀の日程を決めるにあたって、所要時間を把握しておくことは非常に重要です。
しかし葬儀は頻繁に経験するものではないため、所要時間や全体の流れを理解できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、一般的な葬儀にかかる時間を、タイムスケジュールの例とともに解説します。
葬儀の日程を決める際に押さえておきたいポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
葬儀の所要時間

まずは、お通夜と葬儀・告別式にかかる時間の目安をご紹介します。
関連記事:葬儀・葬式の流れとは?ご逝去から葬儀までの手順・段取りを徹底解説
お通夜の所要時間
お通夜にかかる時間は、合計で3~4時間程度とされています。
故人を弔うお通夜の時間を2時間ほど過ごしたあと、1~2時間程度の「通夜振る舞い」とよばれる会食の場が設けられるのが一般的です。
ただし、通夜振る舞いへの参加は自由のため、これに出席しない参列者は2時間ほどで帰宅することとなります。
葬儀・告別式の所要時間
葬儀・告別式は、30分~1時間ほどで終了します。
閉式後、出棺の儀を行ってからご家族と親族は火葬場へ移動しますが、一般の参列者は出棺を見届けた時点で解散するケースがほとんどです。
なお、葬儀の開始から後述する「精進落とし」までの所要時間は、5~6時間程度です。
葬儀の一般的な開始時間
葬儀は一般的に、お通夜の翌日10時~11時頃から始まります。
午前中に開始される理由は、そのあとの出棺や火葬、精進落としなどに時間がかかるためです。
葬儀当日、ご家族は受付開始の1~2時間前、一般の参列者は30分前を目安に会場に集合することとなります。
葬儀にかかる具体的な時間

続いて、葬儀のタイムスケジュールの一例をご紹介します。
葬儀の日程を組む際にお役立てください。
【1日目】お通夜
お通夜は、大切な方が亡くなった翌日の夕方以降に執り行います。
具体的なタイムスケジュールは以下の通りです。
16:00~納棺
納棺とは、清めたご遺体を故人の思い出の品とともに棺に納める儀式のことです。
立ち会うのは基本的にご家族のみで、故人に落ち着いて言葉をかけられるのはこのタイミングが最後となります。
納棺の儀にかかる時間は、1時間前後です。
納棺師とよばれる専門職の方が故人の身だしなみを整え、ご家族一人ひとりがお別れの言葉を告げたら、棺をお通夜の会場へ移動させます。
17:00~親族集合
納棺の儀を終え、お通夜が始まる1時間ほど前になると、親族が会場に到着します。
親族との挨拶をひと通り終えたら、受付の配置やご焼香の順番、出棺時の役割分担などについて、葬儀社の担当者と最後の打ち合わせを行いましょう。
なお、親族はこのタイミングでご家族に香典を渡し、芳名帳への記入を済ませます。
17:30~受付開始
お通夜が始まる30分前を目安に、一般の参列者の受付を開始します。
受付の担当者は、香典の受け取りや返礼品の配布、会場の案内などを行います。
これらは不慣れな作業となるため、参列者全員の受付を終えるまでには、20~30分ほどかかるのが一般的です。
お通夜の規模によっては、さらに時間がかかることも考えられるので、一般の参列者には、時間に余裕をもって会場に到着するよう伝えておくことをおすすめします。
また受付を担当しないご家族や親族は、参列者の誘導や僧侶の出迎えなどを行いつつ、必要に応じて受付の担当者をサポートしましょう。
18:00~お通夜
僧侶の準備が整い次第、お通夜が始まります。
お通夜は、読経やご焼香、喪主の挨拶などを通して故人を弔う場です。
参列者の人数によって多少は変動しますが、通常、1~2時間ほどで終了します。
なお、お通夜は仕事を終えた方々が参列しやすい時間帯である、18時以降に始まるケースがほとんどです。
もしお通夜を平日に執り行う場合には、この時間帯に開始することで、より多くの方が故人を弔えるようになります。
19:30~通夜振る舞い
お通夜を終えたあとには、1~2時間ほどの通夜振る舞いの場が設けられます。
この会はご家族と親族のみで行うケースが多いですが、一般の参列者を招待しても問題ありません。
ただし一般の参列者は、通夜振る舞いにあまり長居しないのがマナーとされています。
そのため故人やご家族、親族との関係性次第ではあるものの、翌日の準備の妨げにならない程度の時間に会場を出るケースがほとんどです。
【2日目】葬儀・告別式
お通夜の翌日には、以下のようなスケジュールで葬儀や告別式が行われます。
9:00~ご家族集合
葬儀の開始時刻の1時間前を目安に、ご家族が集合します。
葬儀では前日の会場を引き続き使用するケースが多く、お通夜のときと同様、葬儀社の担当者と段取りの最終確認を行います。
受付担当や僧侶の出迎え係り、一日の流れなどをここで確認しておくと、一連の儀式をスムーズに進行できるようになるでしょう。
また、高齢のご家族や遠方から参列される親族への配慮も欠かせません。
こうした方々が少しでも快適に過ごせるよう、待合室の清掃や整理整頓は入念に行いたいところです。
9:30~受付開始
葬儀開始の30分前になると、一般の参列者の受付が始まります。
参列者が香典を用意してきた場合はここで受け取りつつ、芳名帳に名前や住所を記載してもらいましょう。
受付のあとは、誘導係が参列者を席に誘導します。
基本的には会場の中央に通路があり、祭壇に向かって左側が一般の参列者の席、右側がご家族や親族の席です。
なお一般の参列者には、遅くとも葬儀が始まる10分前には会場に着席するよう伝えておくと、全体の進行がスムーズになります。
10:00~葬儀・告別式
参列者が揃ったら、葬儀と告別式が執り行われます。
開式後は僧侶の読経から始まり、弔電の読み上げやご焼香、喪主の挨拶と続くのが基本的な流れです。
これらは30分ほどで終了し、参列者は出棺のために会場の外へ移動します。
10:40~出棺
葬儀と告別式の閉式後は、出棺の儀が始まります。
出棺の儀とは、火葬場へ移動する前に棺のなかにお別れの花を手向け、故人の顔を見納める儀式のことを指します。
故人と顔を合わせられるのはこのタイミングが最後なので、生前の厚情に感謝を込めてきちんと見送りたいところです。
なおご家族と親族以外の参列者は、火葬には参加せず、出棺の儀が終わり次第帰宅するのが一般的です。
12:00~火葬・骨上げ
棺が火葬場に到着して焼却炉の準備が整ったら、火葬を行います。
火葬には1~2時間程度の時間を要し、そのあいだご家族と親族は、軽食をとりながら待合室で過ごすこととなります。
この待ち時間は、故人との思い出話に花を咲かせつつ、気持ちの整理をつける大切な時間です。
火葬が終わり遺骨が冷却されたあとは、骨上げの儀式に移ります。
骨上げでは、まず足と腕の遺骨を拾い上げて骨壺に納めます。
そのあとは下半身から上半身にかけて遺骨を納めていき、最後に喪主が喉仏の骨を入れたら儀式は終了です。
関連記事:葬儀なしで火葬のみを行うことは可能?流れや費用相場は?
13:00~精進落とし
骨上げを終えたら、「精進落とし」とよばれる会食の席が設けられるのが通例です。
この会食は、ご家族と親族、僧侶をねぎらう目的で行われます。
1~2時間程度の会となるケースが多く、主に懐石料理や仕出し弁当、故人の好物などが提供されます。
ただし最近では、火葬を待つあいだに待合室で精進落としの料理が振る舞われることも珍しくありません。
葬儀当日のタイムスケジュールを組む際には、どのタイミングで精進落としを行えば全体の流れがスムーズに進むのかを検討するとよいでしょう。
一般の参列者に伝えておくべきポイント

次に、葬儀を執り行うにあたって、一般の参列者へ事前に伝えておくべき2つのポイントをお伝えします。
葬儀をスムーズに進めるためにも、それぞれご確認ください。
時間に余裕をもって来場してもらう
一般の参列者には、葬儀の当日、時間に余裕をもって来場してもらいたいところです。
葬儀には、多くの参列者が集まります。
参列者が多い場合、受付や駐車場が混雑すると予想されるため、葬儀の開始時間に間に合わなくなるおそれがあります。
当日は、遅くとも葬儀開始の30分前には会場に到着するように伝えておくと安心です。
また、葬儀では喪服や香典の用意にくわえて、会場周辺のリサーチなど、普段とは異なる準備が必要です。
出席が決まった段階で、準備を少しずつ始めてもらうよう助言しておけば、当日の混乱を防ぐことができます。
不参加の場合は早めに連絡してもらう
葬儀に来られない参列者には、その旨を早めに連絡してもらうように案内することをおすすめします。
葬儀の準備では、参列者の人数に合わせて座席や食事を手配します。
出席が確定していない参列者がいると、これらの準備は進められません。
とはいえ参列者にも予定があるので、出欠の連絡が遅れることもあります。
余裕をもって日程を調整してもらうためにも、ご案内はできるだけ早めに差し上げましょう。
葬儀の日程を決める際のポイント

最後に、葬儀の日程を決める際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
実際に葬儀のタイムスケジュールを組む際にお役立てください。
火葬場の空き状況
葬儀の日程を決める前には、火葬場の空き状況の確認が必要です。
火葬場の数は、全国的に不足しています。
都市部では特に予約が取りにくく、「葬儀会場は押さえられたけれど、火葬場の空きがない……」というケースも少なくありません。
また火葬場は、宗教上の理由で火葬に向かないとされる友引の日や、年末年始には営業していないこともあります。
直前になって焦らないためにも、火葬場の空き状況は事前に必ず確認しておきたいところです。
なお、空き状況の確認には手間がかかるので、面倒な場合は葬儀社に依頼するのも一つの手です。
僧侶の都合
僧侶の都合も、葬儀の日程を決める際には考慮しなければなりません。
多くの葬儀では、僧侶による読経や法話の時間が設けられます。
これには故人の供養と成仏を祈るとともに、残されたご家族の気持ちを慰める目的があります。
しかし、僧侶の仕事は多岐にわたり、特にお盆やお彼岸の時期は多忙です。
こうした時期には僧侶の都合がつきにくくなると予想されるため、対応可能かどうかを事前に確かめる必要があるわけです。
親族の都合
火葬場の空き状況と僧侶の都合が把握できたら、次に親族が参列可能な日程を確認しましょう。
親族のなかには、遠方に住んでおり移動に手間がかかる方もいらっしゃるかもしれません。
また故人との関係が深かった親族は、「なんとしても最後のお別れをしたい」という思いから、葬儀当日に有休を取得することも考えられます。
こうした方々をはじめ、できる限り多くの親族に参列してもらうには、葬儀のスケジュールを早めに決定して連絡することが大切です。
地域のルールや風習
地域ごとのルールや風習も、葬儀の前に確認しておきたいポイントの一つです。
先ほどもお伝えしましたが、日本には友引の日を避けて葬儀を執り行う風習があります。
「友を引き連れる」という言葉が連想され、縁起が悪いといわれているからです。
こうした風習を把握せずに日程を組んでしまうと、参列者に不快感を与えてしまうかもしれません。
参列者が故人を穏やかに弔えるよう、地域ごとのルールや風習を葬儀の前に確認しておくと安心です。
まとめ
今回は、一般的な葬儀の所要時間やタイムスケジュールの例などをご紹介しました。
大切な方が亡くなったあとは、さまざまな儀式が2日間に分けて執り行われます。
1日目の夕方以降に始まるお通夜は、そのあとの通夜振る舞いまで含めると3~4時間程度の時間を要します。
翌日の午前中に執り行われる葬儀と告別式は30分ほどで終了しますが、精進落としまで参加すると所要時間は5~6時間程度です。
上記の所要時間を参考にして、適切なスケジュールを組みましょう。
なお葬儀・家族葬のかながわセレモニーサポートでは、葬儀のプランを豊富にご用意しております。
火葬場の予約や僧侶との連絡などもサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者

森井 功介
株式会社リコリス 代表取締役
<資格>
<略歴>
1982年神奈川県藤沢市生まれ。20年間で7,500件以上のお別れに立ち会う。2015年に株式会社リコリスを設立し代表就任。現在は「かながわセレモニーサポート」ブランドのもと、追加料金ゼロの総額プランを提供しながら、終活セミナーやエンディングノート講座を通じて地域の終活支援にも注力している。
<代表メッセージ>
「かながわセレモニーサポート」を運営する株式会社リコリスは、追加料金なしの総額プランで“内容と価格の透明性”を徹底。花祭壇を含む高品質なサービスを適正価格で提供し、ご家族一人ひとりの想いに寄り添った“世界に一つだけのお葬式”を実現します。
事前相談や終活サポートにも力を入れ、経験豊富な専任スタッフが不安や疑問を解消し、後悔のない葬儀をお手伝いします。
SNS
かながわセレモニーサポートについて